| |
||
 |
||
|
||
| 2月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
 ものづくり 板材を見ていたある日、これで箱を作ったら面白いだろうなと思いつきました。ただの四角い箱ではなく、六角形にしたらもっと面白いな、と思って、頭の中で完成図だけイメージしてみました。 その何となくを、「作ってみたい」と相談したら、モノづくりの先生、ぎっくは、「まあ、やってみれば?」と応援してくれました。「まず、六角形の型を作ると良い」とアドバイスもくれました。 自分でも単純だなと思うけれど、応援されると頑張ろうという気持ちが大きくなる。頭の中のぼんやりしていた完成図も、何から手を付けたらよいかがわかると、具体的な設計図にできました。ひとたび手を付けてしまえば、そこからはだんだん出来上がっていくのが楽しくて、どんどん進みました。途中でどうしたら良いかわからなくなっても、困っていることを口に出せば、一緒に考えてくれる人もたくさんいました。 やりたいと思ったことを言葉にして、口に出してみる。そうすると、力を貸してくれたり、応援してくれたりする人が集まってくる。すごく素敵だなと思います。 今回は木工だったけれど、他の事も同じだと思います。自分の考えていることは、言葉にしなければ誰にも伝わらないし、伝わらなければ応援も意見ももらえません。 だから、まずは悩んだりする前に、「言葉にする」「口に出す」をやってみようと思いました。 何かを作るためには道具を使う。使える道具の幅が広がると、できることの幅も広がると感じることが多い。例えば、のこぎりが木を切る道具だということは知っているので、板材に線を引いて、のこぎりで切り出そうとしました。そのとき、私が使おうとしていたのは、一般的な横引きのこぎりでした。「木目に対して並行に刃を入れるときは縦引きの方が切りやすい」と、縦引きのこぎりを貸してもらうと、確かに、横引きののこぎりで縦に切るより、早く綺麗に切れました 他にも、木のお椀を彫ったとき、自分の小刀で削ると結構硬くて、腕や指先に変な負荷がかかったけれど、よく研がれている小刀を借りて作業すると、びっくりするほど簡単に削れるのです。その上、削った後の表面が滑らかで、つやっぽく仕上がります。 お椀なので、新聞紙を広げれば、どこでも作業できる。ただ、丸い形は木工台で固定しようとしても、コロンと転がってしまうので、万力(固定するための道具)を使うこともありました。固定がしっかりしていると、刃先にしっかり体重をかけながら力を加えられる。固定の良し悪しでも、その日の進み具合が変わるのがよくわかりました。 ただ、一辺切るごとにのこぎりを持ち換えたり、向きを変えるために万力を外したりすることを、面倒くさいなと思うこともありました。その面倒くささをどうしたら少しでも減らせるのか?を考えて工夫するようにもなりました。 同じ道具で切るものをまとめて作業したり、万力の代わりに自分の足や手で押さえてみたり、回数を重ねると当たり前のように効率化できるのです。何かをやってみて、うまくいかないこともあって、そこからどうしたらより良くできるかを考える。これが学びなのだなと思いました。 相談員で薪小屋の材を、もう材としては使わないものと、今後材として使うものに分けていたとき、木目が詰まっていて、きれいだなと思うものがありました。家の建材に使われていた柱で、表面は汚れていたし、だいぶ年季がたっていたので、もう材としては使わない方に分けられていました。もったいないなと思っていたとき、「何か作れるんじゃない?」と言われて、とりあえず、とっておきました。  うまく材になるか不安でしたが、ぎっくに相談するとクサビや電動工具を駆使して、表面を削り、材にしてくれました。削ってみると、天然の檜だとわかりました。カンナで少し削っただけで、周辺に檜のよい香りが広がり、詰まった綺麗な木目が出ていました。 うまく材になるか不安でしたが、ぎっくに相談するとクサビや電動工具を駆使して、表面を削り、材にしてくれました。削ってみると、天然の檜だとわかりました。カンナで少し削っただけで、周辺に檜のよい香りが広がり、詰まった綺麗な木目が出ていました。木べらを作ることにしたが、本当に綺麗で、作る前から早く完成を見たいと思いました。四角い柱を見つけた時は、こんなに惹かれる材になるとは思っていませんでした。やってみて良かったです。自分にとって価値あるものは、はじめからその形をしているとは限らない。自分で見つけて、自分の手で価値あるものにしていくのだなと思いました。 檜つながりで、もう一つ、印象的なことがありました。たまたま、檜の丸太の皮むきを見る機会がありました。手づくりの竹のヘラでペリペリ剥くのを見ているのも面白かったが、そのあとにもっと面白いことがありました。皮を剥くとき、幹に傷がつくとそこに樹液が溜まる。「なめてごらん」と言われて、樹液を舐めてみました。当然、甘いのだと思っていました。想像と違って全く甘くありませんでした。それどころか、かなり癖の強い味で、目が覚めるような刺激的な後味がしました。 今までずっと、木の樹液は花の蜜のように甘いと思っていました。小さいころ、花の蜜を吸って遊んでいたのを思い出します。その記憶から、植物の蜜は甘いものだと思っていたのかもしれません。カブトムシが樹液に集まる様子と、捕まえるためにバナナやはちみつを使うことも、樹液が甘いという想像の助けになっていました。 何事も経験してみないとわからないけれど、経験したことは自分にとって当たり前になり、疑うこともしなくなる。いつの間にか、知っていることが当たり前になっていました。知りたいとか、疑ってみる気持ちを久しぶりに感じて、わくわくしました。 仲間の覚悟  3学期になって、全体としてやりきろうという雰囲気も出てきていました。登り窯も、12月と比べて、自分たちで考えてできたという達成感あり、とても良いものでした。 3学期になって、全体としてやりきろうという雰囲気も出てきていました。登り窯も、12月と比べて、自分たちで考えてできたという達成感あり、とても良いものでした。しかし、その中で、こどもたちの中から、だいだらぼっちの暮らしを壊してしまうようなものが見つかりました。こどもたちも、信頼していた仲間の、思いがけない行為に打ちのめされている様子もありました。私も頭では理解しても、心では受け入れたくないと感じました。 話し合いを設けて、一人一人の言葉を聴きました。その時のこどもたちの言葉や表情が、これまでの色んな出来事や話し合いで、確実に何かが積み重なっているのだと感じられました。相手を許すという子も許したくないという子も、自分の本心で相手と誠実に向き合っていました。 積み重ねてきた信頼が崩れたとしても、積み重ねてきた過程は無駄にはならないと感じました。もう一度みんなの覚悟を確かめることになり、ここまで一緒に暮らしたからこその実感のある覚悟がたくさん聴けました。私も、こどもたちと同じように、もう一度覚悟を持てました。 がっかりしたし、できれば起きてほしくなかったことだけど、仲間の覚悟やだいだらぼっちへの思いを確かめる良い機会になったことは確かだと思います。つまずきを次へのスタートにするのもしないのも自分たち次第で、次につなげるのは、それまで自分たちが見せてきた姿。それを実感しました。同時に、何があっても、1年間一緒にやりきるということの重さも感じました。 |
||
□ 研修担当なおみちのふりかえり  かなぽんは、だいだらぼっちのこどもたちが一年の暮らしをやり切って未来へ向かえるようにサポートすることと、木工にチャレンジすることを目標に2月を過ごしました。 かなぽんは、だいだらぼっちのこどもたちが一年の暮らしをやり切って未来へ向かえるようにサポートすることと、木工にチャレンジすることを目標に2月を過ごしました。忙しい暮らしの中で、すき間の時間にサッと小刀と木材を取り出しては削るという情熱を見せたかなぽん。「いい匂いなんですよ〜♪」と板になったヒノキを私に嗅がせてくれたあの嬉しそうな顔が思い出されます。 また、実はこどもと本気で喧嘩して涙を流したことがありました。「わたしが本気で喧嘩するなんて…」と言いつつも、相手と本気で通じ合った感覚も覚えていました。こどもを支えたいという気持ちが本物であったということを物語っています。 「自分の気持ちを言葉にして相手に伝えることが課題」というかなぽんは、身の回りのささやかな一つひとつに感動したり、怒ったりできる素直な感受性を持っているのだと感じます。単純で浅はかというのとは全く違います。ただ、そのふんわりと色のような温度のような形で感じているソレを、言い当てる言葉が見つからなくて苦しい!と感じているようです。それでも、輪郭のぼんやりした感覚や感情、学びの核心を言葉にすることをあきらめずに続けることで自分と向き合い、道を拓いてきました。この成長のプロセスを、ぜひ忘れないでいてほしいです。 ぷすぷすとくすぶって表現できなかった感覚は、言葉にすることで何だか自分から遠のいて普遍的なものにすり替わり、自分だけの感動や不安、悔しさなどは薄れていくものでもあるように思います。しかし、この感覚にこそ、自分の育ちへの願いが込められているのではないでしょうか。そして、かなぽんはこのことをはっきりと感じ取っています。だから、悩んでも落ち込んでも必ず這い上がってこられました。 そうやって自分を見つめて信じてこられたかなぽんだからこそ、言葉にならないこどもの思いをわかってくれる、こども自身がもっている育ちの力を信じて寄り添ってくれる、そんな先生になってくれると確信しています。 |
||
| 1月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
冬休みあけの覚悟  冬休みがあけて、全員がそろった日、はじめの会をしました。毎年恒例になっていて、冬休みの思い出と、来年度、ここにもう1年残るかどうかの決意を表明する場でもあります。冬休みに入る前、どうしようかなと悩んでいた子も、冬休みの間に覚悟を決めて、ここで発表します。 冬休みがあけて、全員がそろった日、はじめの会をしました。毎年恒例になっていて、冬休みの思い出と、来年度、ここにもう1年残るかどうかの決意を表明する場でもあります。冬休みに入る前、どうしようかなと悩んでいた子も、冬休みの間に覚悟を決めて、ここで発表します。こどもたちの中には、保護者と十分に話ができて、自分の出した結論に納得している子も、そうでない子もいる様子でした。でも、タイムリミットのこの場では、自分の口で決意を言わなければならない。結論に迷いがある子にとっては、苦しい場だろうと思いました。 それでも、相談員もこどもも円くなって、一人一人の決意を聴くことが、すごく大事なことなのだと感じました。自分で決めたことが、自分を含めた仲間全員に受け止められる。それが、自律につながるのだと思いました はじめの会のあと、自分の出した結論に悔いが残っている子もいました。でも、そこで悩むよりも、残された3学期をやり切ると気持ちを切り替えて、少しでも時間が生まれたら、木工をしたり、ご飯隊に積極的に手を挙げたりして、過ごしていました。その姿に影響されて暮らしを頑張っている子も増えました。私自身も、その姿を見て、改めて残っている時間をどう過ごすのかを考えました。 このはじめの会が、仲間の決意とともに自分のことも考える良い機会になるのは、ここまで仲間の声を聴く事を大事にしてきたからだと感じます。 暮らしが落ち着いていた1月  1月は、こう表現することが正しいのかわからないけれど、これまでに比べて、びっくりするくらい落ち着いていました。予定されていたもの以外の話し合いをするようなこともなく、それぞれが木工や、その他やりたいことに打ち込める時間がありました。 1月は、こう表現することが正しいのかわからないけれど、これまでに比べて、びっくりするくらい落ち着いていました。予定されていたもの以外の話し合いをするようなこともなく、それぞれが木工や、その他やりたいことに打ち込める時間がありました。毎月何らかの事件が起きて、話し合いを繰り返していたような感覚があるので、どこか拍子抜けしました。けれど、本来なにもなければ、これが通常の暮らしなのだと思います。ただ、みんなで暮らしていれば色々ある。その時は話し合いをして想いを聴く。それが思った以上に自分に染み込んでいたのだと気が付きました。 暮らしが落ち着いていると、こどもたちとゆっくり話したり、時間に焦ることなくご飯づくりができたり、丁寧にできることが多かったです。話し合いの中で聴ける想いや本音もあるけれど、一緒に何かをする時に、ふいに聴けることもたくさんある。それを感じました。一緒にお風呂に入る時間、ご飯づくりの最中、ゆっくり話をしました。私にとっては、その時間がすごく有意義でした。普段、話が出来ない子や、少し元気がなさそうだな、など関わろうと思ってもタイミングを逃してしまっていた子たちとも時間を持てました。  こうして意識的に向き合う時間を持ってみると、話し合いがたくさんある時や、問題が起きた時は、私自身も余裕がなくなっていたのだなと思います。自分の中の向きあうエネルギーを話し合いに使い過ぎてしまっているのだろうと。自分に余裕があると、色んなところに目を向けられる。普段から、その余裕を持てるようにしたいなと思いました。例えば、予期せぬ話し合いがあったとしても、それを話し合い以外の時間にも引きずり過ぎず、心を整理できれば、他のことに目を向けられると思います。他のことを見ることで、そのとき起きている事件をかえって客観的にみられることもあると思う。こどもたちは敏感に相談員の様子を察している。相談員に余裕があると感じれば、気軽に話かける。逆に、余裕がなさそうと感じると遠慮している。それがこどもたちなりの優しさであるのかもしれないが、そういうことを気にせずに、話を聴いてほしいその時に、側にいてあげられるようになりたいと思いました。そのためには、常に他のことを受け入れられる心の余裕を持てるようにしたいです。 こうして意識的に向き合う時間を持ってみると、話し合いがたくさんある時や、問題が起きた時は、私自身も余裕がなくなっていたのだなと思います。自分の中の向きあうエネルギーを話し合いに使い過ぎてしまっているのだろうと。自分に余裕があると、色んなところに目を向けられる。普段から、その余裕を持てるようにしたいなと思いました。例えば、予期せぬ話し合いがあったとしても、それを話し合い以外の時間にも引きずり過ぎず、心を整理できれば、他のことに目を向けられると思います。他のことを見ることで、そのとき起きている事件をかえって客観的にみられることもあると思う。こどもたちは敏感に相談員の様子を察している。相談員に余裕があると感じれば、気軽に話かける。逆に、余裕がなさそうと感じると遠慮している。それがこどもたちなりの優しさであるのかもしれないが、そういうことを気にせずに、話を聴いてほしいその時に、側にいてあげられるようになりたいと思いました。そのためには、常に他のことを受け入れられる心の余裕を持てるようにしたいです。 |
||
□ 研修担当おらふのふりかえり  1月を振り返ったかなぽんの第一声が「落ち着いていた」であったことから、これまでは目を向ける余裕のなかった暮らしの部分にまで視野を広げることができた1か月だったと感じました。視野が広げられたことによって、こどもとの関わりに深まりが生まれただけではなく、かなぽん自身を見つめられる時間が生まれたと思います。1月までかなぽんと共に暮らしてきた中で、かなぽんはどんな状況であっても自分自身を見つめ、今の自分に足りてないところは何か、そこを補うためには具体的にどうすればよいかを自分で分析し次に進んでいける人だと感じていました。なので、「落ち着いていた」1月は自分自身を見つめ磨き続けるかなぽんを、さらに成長させる1ケ月だったと思います。その証が、最近のかなぽんの前向きな発言や、こどもに寄り添う姿から感じられます。 1月を振り返ったかなぽんの第一声が「落ち着いていた」であったことから、これまでは目を向ける余裕のなかった暮らしの部分にまで視野を広げることができた1か月だったと感じました。視野が広げられたことによって、こどもとの関わりに深まりが生まれただけではなく、かなぽん自身を見つめられる時間が生まれたと思います。1月までかなぽんと共に暮らしてきた中で、かなぽんはどんな状況であっても自分自身を見つめ、今の自分に足りてないところは何か、そこを補うためには具体的にどうすればよいかを自分で分析し次に進んでいける人だと感じていました。なので、「落ち着いていた」1月は自分自身を見つめ磨き続けるかなぽんを、さらに成長させる1ケ月だったと思います。その証が、最近のかなぽんの前向きな発言や、こどもに寄り添う姿から感じられます。また、話し合いの中で聴けるこどもの想いや本音に加えて、暮らしの「ふとした瞬間」のこどもの声に耳を傾けられるようになったかなぽんは、すでに心に余裕のある人になれていると感じました。こどもたちは日々の暮らしを共にするが故に気持ちの揺れ幅が大きくなりますが、かなぽんの寄り添って話を聴いてくれる姿に支えられています。 「落ち着いていた」1月を経て、常に他のことを受け入れられる心の余裕を目指すかなぽんを側で応援しています。 |
||
| 12月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
 登り窯 だいだらぼっちでは今年度初めての登り窯がありました。継続している子から、新規の子へのレクチャーを聴いていると、本当に自分たちで考えてやっていること、そこにすごく熱意を持っていることを感じました。 実際にやってみると、私が今まで炎だと思っていたものは何だったのだろうと思うような、熱と光を感じました。1回の担当時間である4時間があっという間に過ぎてしまう。そういう感覚がありました。こどもたちが主役なので当たり前と言えば当たり前だけれど、当然のように「次、どうする?」「温度上げるなら薪増やす?」と考えあう姿にすごいと思いました。仲間の感覚、自分の感じたことを信じていて、目指す窯の状態があって、そこに向かって何が必要かを考える。たくさんの話し合いを重ねてきた、12月の今だからこそ、できることだと感じました。こどもたちと一緒に考えることは、すごく面白かった。物が燃えるには酸素が必要という当たり前の知識を、窯の状態と照らし合わせて、煙突の開け方を考えました。学んだ知識が活きる体験がこんなに興奮するものだとは思いませんでした。これまで作ってきた作品が焼きあがって、窯から出てきたとき、作品が出来上がった喜び以上の達成感がありました。一つの作品が出来上がるまでの、長いストーリーを読んだような気持ちになった。粘土をこねているときのことを思い出して、ものづくりの奥深さに少し触れたような気がしました。  次の登り窯が楽しみだというこどもたちの声を聴きました。私も同じだった。1度この感覚を味わってしまったら、もう一度、やりたくなってしまう。すでに次の登り窯に入れる作品を考えている子を見て、私も次はどうしようかな、と考えました。 次の登り窯が楽しみだというこどもたちの声を聴きました。私も同じだった。1度この感覚を味わってしまったら、もう一度、やりたくなってしまう。すでに次の登り窯に入れる作品を考えている子を見て、私も次はどうしようかな、と考えました。冬キャンプ 相談員として参加経験のあった夏キャンプとは異なり、冬キャンプは完全に初めてでした。どういうアクティビティがあるのか、フィールドの中でどんな遊びが広がるのか、全く想像がつかなくて、それが楽しみでもあり、不安でした。 キャンプが始まると、こどもたちの遊びの広がりは想像以上でした。あるものを使って工作をしたり、的当てをしたり、本気の鬼ごっこに夢中になったり、まさに遊びは無限だなと感じました。夏のキャンプは川遊びという、わかりやすく楽しい遊びがあるけれど、冬は何も遊ぶ事がないのではないかと、勝手に心配していた自分が、楽しむ心を忘れかけていたなと思いました。一緒に遊ぶ仲間がいて、自由な空間と時間があれば、それだけで魅力的なんだと思い出したような気がしました。 不安に感じていたことは、とにかく準備と練習を万全にすることで、少しでも減らしました。考えられるアクティビティで、ピザ焼きや餅つきなど慣れが必要なものは出来るだけ事前に練習しました。実際にやってみると、どこが難しくて時間がかかるのか、気をつけるところはどこか理解できました。説明してもらうだけではわからない感覚のところまでつかめたことで、自分一人でやる場面になったときに、「練習したから大丈夫」と落ち着いてできた。 練習は実際にやってみて手順を覚える意味合いが大きかったが、私にとっては1度やったからできるはず、という心理的な安心感を得られた事が大きかったです。 一方で、初めてのことや経験の少ない事には及び腰になる自分を再認識した出来事でもありました。「とりあえずやってみよう」と子どもにはチャレンジを促すけれど、失敗が怖くなって、できるだけ準備しようとしている自分はどこか矛盾しているなと思いました。キャンプの安全管理の面からも、私がしっかり練習して対応できるようにすることは当然必要なことではあると思いました。けれども、心持ちとして、先手を打つばかりでなく、何もわからないけれど、やってみよう!というチャレンジの心を、もっと持ちたいと思いました。  また、冬キャンプは夏キャンプに比べて、自分の中で切り替えがうまくできなかったことが課題でした。夏キャンプのときも、だいだらぼっちとキャンプの切り替えが大事だとアドバイスをもらお、夏キャンプはだいだらぼっちの1学期終了のあと、すぐに現場ではなかったので少しずつ気持ちをキャンプに寄せられたと思います。 また、冬キャンプは夏キャンプに比べて、自分の中で切り替えがうまくできなかったことが課題でした。夏キャンプのときも、だいだらぼっちとキャンプの切り替えが大事だとアドバイスをもらお、夏キャンプはだいだらぼっちの1学期終了のあと、すぐに現場ではなかったので少しずつ気持ちをキャンプに寄せられたと思います。今回は、終わった日の夕方にキャンプが始まりました。そこで全くと言っていいほど、気持ちを切り替えられず、だいだらぼっちでのモヤモヤを引きずってしまい、なかなかキャンプを楽しむ気持ちになれなかった。それでも、なるべく気にしないように、目の前のことを確実に、と一つずつやるべきことを重ねるうちに、だんだんキャンプに集中していきました。自分では、私の気持ちがどうであれ、キャンプが始まるのだから、顔にも態度にも出さないようにと心がけていました。でも、気持ちを切り替えられたな、と思ったタイミングで、「元気になってよかった」と言われ、実際は周囲に心配をかけていたことに気がつきました。 そのとき、心配してくれる仲間がいることのありがたさ以上に、人と一緒に何かをやるときに、そこに向かって自分を整えることは、自分一人の問題ではないということに気が付きました。万全の状態をつくろうとしている人の気持ちに応えるためにも、切り替えが大事と言われていたのだとわかった。 キャンプだけでなく、誰かと何かをするという場では、同じことが言えると思います。今後の課題として、気をつけていこうと学びました。 |
||
□ 研修担当だいちゃんのふりかえり  登り窯では、自分の中にある知識を越えた自然を感じたと思います。キャンプでの火起こしとはまったくレベルの違う1200度の炎の迫力は凄まじかったのではないでしょうか。そして、その炎まで達するために積み上げた、こどもたちと大人の団結したあの瞬間はかなぽんの財産になったと思います。 12月は、こどもたちとの関係で「どう接するか」「なにをすべきか」「なにを話すか」など悩みや葛藤もあったかと聞きました。その中での登り窯は普段の生活とは違い、登り窯の真っ最中だからこそ、言える本音やありがとうの言葉があります。登り窯を終え、より強くこどもたちや相談員との関わりを深められたと思います。 冬キャンプでは、初めてのことが多く戸惑ったと思います。夏のキャンプでは川あそびが王道ですが、冬キャンプは「コレ!」といった王道はありません。だからこそ自分たちで遊びや楽しさを作っていける現場でもあります。冬キャンプで出会ったこどもたちとかなぽんが笑顔で遊んでいる姿を見て安心しました。また、かなぽんは冬キャンプの全日程に参加しました。お年とり料理や馴染みのない場所への探検など大変なことが沢山あったと思います。そんな時もかなぽんは「一回、下見に行ってもいいですか」「ごはんづくりの段取りとってもいいですか」と不安を解消してキャンプに望みたいというポジティブな想いで乗り越えてくれました。準備があるから本番に自信を持って迎えられる。かなぽんの表情からはそんなことが伺えました。この普段の日常とは違うことが多い12月の出来事を今後の生活に役立ててほしいと思います。 |
||
| 11月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
11月は、10月から準備を重ねただいだらぼっち祭りがあったほか、山から木を倒して採ってくる山出し、次年度の仲間集めのためのだいだらぼっち説明会があったりと、全体的に忙しい、という印象だった。 忙しいからこそ、普段の暮らしをより丁寧にするよう心掛けたり、自分たちでうまく時間をやりくりする必要があって、そこが面白いところでもあった。 山仕事  初めて山仕事という経験をした。山仕事と言われてもほとんど何もイメージできず、木を倒すというのも、絵本でみたような斧で倒す画しか想像できなかった。 初めて山仕事という経験をした。山仕事と言われてもほとんど何もイメージできず、木を倒すというのも、絵本でみたような斧で倒す画しか想像できなかった。なので、実際にスタッフと一緒に山に入って、一つずつ仕事を見られるのがとても面白かった。 必要な道具、服装、すべてが理にかなっていて、知恵が蓄積されていることを感じた。 斜面に対してまっすぐ上の方向で登ろうとすると山が崩れるので、斜め上方向に進むように言われた時、まず山が崩れるという考えが自分の中に今までなかったことで、驚いた。 次に、斜めに登ると山が崩れにくいこともそうだが、何より自分が格段に登りやすく、自然にとっても上る人にとっても合理的な方法だと思った。 木の見分けはほとんどつかないだろうと思っていたが、薪作業でお風呂用の針葉樹、ストーブ用の広葉樹と分けていたり、木工で使いやすい材を少しずつ覚えていたりしたので、わかるものもあった。そうやって自分にもわかるものがあると、他のものにも興味がわいた。 学校行事等で山登りをしたことはあったが、そこで山に興味を持ったり、観察したりしたことは無い。例えば、知識のある人と行ったり、事前にその山の植生を調べたりするだけでも、もっと楽しめただろうと感じる。同じことをしても、その前後の学びで深まり方が全く違うものになると感じた。 自然との共生がテーマの評論文を国語の教科書で読んだことがある。その時は文面を追って、内容を分かっただけだったけれど、山と暮らしが一体である暮らしをしてみると、それ以上に腑に落ちる感覚があった。そういうことなのだと思う。  子どもたちと山から薪を持ってきたことも印象深い。 子どもたちと山から薪を持ってきたことも印象深い。スタッフで山仕事をするのとは違って、子どもと活動するときには安全管理という視点が必要で、考えるポイントが変わるのも面白いと思った。 子どもたちと活動するとき、1番の目的を何にするかによって、事前のアプローチや使う道具も違う。準備をどれだけしておくかで、できることが変わることを感じた。 本番の前に、練習で一度山に行った。現場を見て、実際にやってみて、子どもが自分たちはどこまでできるのかを考えた。色んな道具がそろっているから、やろうと思えばできることは多い。何を大事にするかによって選択が変わる。自分たちがやりたいこと、できることは何かを考えた。どんな役割が必要かも話し合い、当日の動きをみんなで確認した。 作業本番は、事前の役割分担がうまく機能して、スムーズに進んだ。全員が事前の話し合いによって、仕事全体を把握していたので、次にやることや段取りがわかっていた。 山仕事全体を通して、他の活動にも言えることだけど、安全管理と子どもの手に委ねることのバランスが難しいと感じた。 子どもたちが話し合って決めたこと、それ以上に優先されるのは安全の確保であることは、頭ではわかっていた。だが、実際に子どもたちと山に入る前に、相談員でリスクの洗い出しをしたり、子どもがやる仕事が決まった後も当日の安全管理を徹底しつつ、子どもが主体となって動くために、どんな体制が必要か、細かく段取りをとって、安全管理が実際はどれだけ大変な事なのか分かった。 説明会  来年度の仲間集めのために、子どもたちが東京と名古屋に出張して、だいだらぼっちの暮らしを説明する説明会があった。東京チームと名古屋チームに分かれて、準備を進めた。 何も知らない人にだいだらぼっちとは何かを伝える。どうしたら自分たちの思いが伝わるのか考えて、それぞれ工夫していた。 その中で特に印象的だったことがある。 それは、普段、話し合いで積極的に発言したり、声をだしたりする印象のなかった子が、リーダーシップを発揮していたこと。 10人のチームをまとめる役割になり、「集まろう」とみんなに声をかけて段取りをとったり、ただ声をかけるだけではまとまらないと気づいてから、声のかけ方を工夫したり、自分がやれそうな方法を考えたりしていた。上手くいかないと泣いていたこともあったが、そこから、次は何ができるだろうと考える姿は、可能性の塊だなと思った。 当日、帰ってきたときの顔がやり切った笑顔で、「大変だったけど、楽しかった。やってよかった」と言っていて、リーダー的な立ち位置が彼女を成長させたことを感じた。 説明会が終わったあとも、司会に立候補したり、話し合いでの発言が増えたり、どんどん積極的に楽しむようになった。 説明会は彼女にとって大きな意味があったが、それをきっかけにどんどん前に進んだのは、彼女自身の気持ちや覚悟があったからだと思う。1学期からなりたい自分のイメージをしっかり持っていて、少しずつそこに向かって変わろうと努力していた。 そういう姿には、周りの子も刺激されているし、私もよい影響を受けていると思う。  10月を踏まえ、この1カ月は、思ったことを積極的に声に出すように心がけた。ただ、何か思ったときに、気になった子に直接声をかけることの方が多かった。 10月を踏まえ、この1カ月は、思ったことを積極的に声に出すように心がけた。ただ、何か思ったときに、気になった子に直接声をかけることの方が多かった。それがかえって良かったように思う。その子の反応でどう伝わったのか、伝わらなかったのかがわかるし、言い方を間違えたなと思ったらその場で謝ったり、言い直したりすることができる。 そういう積み重ねを意識してみて感じたことは、大事なことは、全体の場や話し合いよりも、日常会話でふいに口から零れ落ちることがあるということ。お互いにかしこまっていないので、身構え、心構えを作らずに済むし、私自身も素直に向き合えていたので、相手も素直に心を開いてくれるのかなと思った。だけど、その分、自分の未熟さを突き付けられることもある。素直に話ができる反面、その場で思ったことを伝えなければならない。自分自身の考えがしっかりしていないと、ぶれてしまって、不信感につながりかねない。 大人子どもに関わらず、相手と誠実に向き合う、その基本が大事であることを、改めて感じた。 |
||
□ 研修担当ゆべしのふりかえり 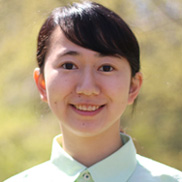 だいだらぼっちの山仕事は、お楽しみのアクティビティではなく、大人もこどもも本気の時間であることを一緒に感じていたと思います。 だいだらぼっちの山仕事は、お楽しみのアクティビティではなく、大人もこどもも本気の時間であることを一緒に感じていたと思います。安全管理の側面でいうと、リスクの多い山仕事であるからこそ、相談員も毎年研修を重ねて、安全管理できるチームになって臨んでいます。かなぽんにも一緒に参加してもらい、この場にこどもがいたら…と想像しながら山に入りました。大切なのは、みんなが暮らし(今回なら山仕事)から手を離さないようにできること。こどもだからやらせられない、でなく、「自分にできること」をこどもたちも下見を通して現場のことを考えられたのです。それぞれ役割があれば、小柄な小学生も、継続のメンバーも関係ない。責任をもってその場で活躍できるのです。そんな「みんな」のマンパワーを信じてやり切った山仕事でした。 一緒に暮らしているからこそ、気になっても、スルーしてしまったり、後で伝えればいいかな…と思う場面がたくさんあったと思います。けれど、大人だって「未熟」。いつも正しいというわけではないなく、時に焦ったり、言い過ぎたり、言い方を間違えることもあります。間違ったら、謝ったり、言い直すことができればいい、かなぽんのいう通りです。あとは、大事なことを伝えるツールが、日常会話でふいにこぼれ落ちることがあってもよいということ。あえて時間をつくることだけが方法と思いこんでいたことそのものも、大事な発見ですね。きっとそこに至ったのも、1年の暮らしだからだと思います。あなたも、1年一緒に暮らす仲間である。私たちは、いつでも日常であり、裏も表も見せ合っています。かなぽんの中にある、素直な言葉を自然にだすこと、その勇気をわたしも時々感じます。その一瞬に救われ、積み重ねが信頼を生んでいる最中。わたしも、みんなも、かなぽんからよい刺激・良い影響を受けています。 |
||
| 10月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
だいだらぼっち祭りに向けて  10月は、11月に行うだいだらぼっち祭りに向けての準備や、発表する劇の練習などに時間を使いました。相談員も、一緒に祭りを作り上げる一員であることを、こどもたちも相談員も当たり前の事実として受け入れていて、暮らしの仲間になれていることを実感しました。 10月は、11月に行うだいだらぼっち祭りに向けての準備や、発表する劇の練習などに時間を使いました。相談員も、一緒に祭りを作り上げる一員であることを、こどもたちも相談員も当たり前の事実として受け入れていて、暮らしの仲間になれていることを実感しました。祭りに向けて、こどもたちは役割を分担して係を立ち上げ、係としての活動がメインになります。例えば、当日の食事を作ったり、メニューを考えたりする人は、食事係として、祭りまでの期間で必要な準備をすべて行います。 私は、五平餅係(当日の朝食で出す五平餅の準備と段取りをする)と、音響係(劇に合う曲や効果音を用意して、演者の動きに合わせて流す係)をやることになりました。9月の振り返りを踏まえ、こどもたちとよいチームを作ることを目標に取り組みました。 結果は、9月に行った二つのイベントと同じく、片方はうまくいき、もう一方はやりきれないところもありました。 まず、9月と同じく、対一人のこどもである音響係では、良い関係性を築くことができました。具体的には、互いの意見を聴き合い、双方が納得できる結論がでるまで、妥協せず、根気よく作業できたことです。始めに二人で目指すゴールを確認し、作業方法について意見を出し合って決めました。互いに納得するところから始めたので、互いの立場が平等になって、意見が言いやすくなったと感じました。 それに加え、二人で決めた音楽が劇の練習で実際にどんどん使用され、成果が即時に可視化されるので、さらにやる気が出るという良い循環を生んだと思います。  一方、複数人で構成された五平餅係ではうまく関係性を築けませんでした。チーム内で経験のある者とない者で意見の強弱があり、相手の言葉に耳を傾けられなかったのです。「正解がわかっている」という意識のあるこどもの態度や正解だと思われる意見に引っ張られ、他の子が遠慮して口を開きにくくなりました。結果として、一人の考えでどんどん話し合いが進んでしまい、他の子がチームでの居場所や自分がチームにいる意味を見いだせなくなってしまったのです。 一方、複数人で構成された五平餅係ではうまく関係性を築けませんでした。チーム内で経験のある者とない者で意見の強弱があり、相手の言葉に耳を傾けられなかったのです。「正解がわかっている」という意識のあるこどもの態度や正解だと思われる意見に引っ張られ、他の子が遠慮して口を開きにくくなりました。結果として、一人の考えでどんどん話し合いが進んでしまい、他の子がチームでの居場所や自分がチームにいる意味を見いだせなくなってしまったのです。私はその状況に向き合い、チームの雰囲気を作っている子に対して何らかのアプローチをするべきでした。 しかし、日常の暮らしの中でも、バタバタしていることがあったため二つのことに同時に向きあう気力を持てず、五平餅係に関しては、向き合うことから逃げてしまいました。結果、滞りなく当日を迎えるための段取りや作業を一人で引っ張りすぎてしまったと感じています。 振り返りで、この話をしたとき、「その子に向き合う必要があったのは本当にかなぽんだったのか」と言われ、ハッとしました。私は、自分がまかされたことなのだから、向き合って話をすることも、私がやるのが当然だと思っていたのです。  しかし、自分とこどもの関係性を考えた時、私よりもその子に届く言葉が言える人はいて、そういう人に相談したり、一緒に話をしてもらったり、方法は他にもあったと気づいたのです。 しかし、自分とこどもの関係性を考えた時、私よりもその子に届く言葉が言える人はいて、そういう人に相談したり、一緒に話をしてもらったり、方法は他にもあったと気づいたのです。相談員に限らず、この子なら落ち着いて話ができるだろうなという子もいました。そういう子に力を貸してもらったり、こども同士の関わりの中で良い方向に持っていけるように、言い方は悪いかもしれないが、上手に根回しできればよかったなと思いました。 それは、自分一人では思い至らず、流れてしまったことだと思います。客観的に状況を見られる人から意見をもらうと、自分では気が付けないことや、見逃していることを拾ってもらえます。 誰かに話を聴いてもらうことは、自分が気付かないことに気が付くきっかけになる。それを感じた出来事でした。 劇の練習、準備全般 劇は音響と照明を除く18人が出演しました。練習では、積極的に声を出す子も多く、誰かに対して改善点を提案したり、「もっとこうしてほしい」などの意見もはっきり言い合えている雰囲気でした。 複数のチームに少人数でわかれている係とは違い、劇では一人一人に明確な役割があり、全体に対して自分が担う役割と責任がわかりやすい。 それが全体から求められているという意識、自分がこの仲間の一員であるという帰属感につながったのではないかと思います。そうすると、もっと良くしていきたい、そのために発言しよう、という想いになったのだと思いました。 また、個人ができることに差があっても、全体としての到達目標がわかりやすかったため、そこに向かって助け合う姿勢が見られました。目標を達成するまでに、何が足りていないかわかりやすかったこともよかったのだと思います。 例えば、劇の完成のためには衣装が全員分必要である。衣装づくりが遅れていたら、そこを手伝う。演技が不安な子には、相手役として練習に付き合う。 わかりやすく目に見える目標というのは、こどもにとって大事なものだなと思いました。 全体として  劇の練習など良い雰囲気の一方、互いに言いたいことがあっても気持ちを飲み込む場面も見られた。仲間に対する遠慮や、自分が意見していいのかという葛藤がその背景にあるのかもしれない、と五平餅係を経て考えるようになりました。 劇の練習など良い雰囲気の一方、互いに言いたいことがあっても気持ちを飲み込む場面も見られた。仲間に対する遠慮や、自分が意見していいのかという葛藤がその背景にあるのかもしれない、と五平餅係を経て考えるようになりました。その葛藤はどこから来るのだろうと思うと、相手が自分の意見を受け入れてくれるのかという不安や、自分の意見と相手の意見が異なったとき、どうしたらいいのかを考えきれていないのかなと思いました。私を含めて、自分がこの場を作っている意識をもって、みんなが意見を言いやすい雰囲気、意見を受け入れる姿勢をもって生活することが、自分自身も意見を言いやすくなることに繋がっていると思います。 11月に向けて 自分の課題として出ていた、言いたいことを言えない、ということへの取り組みとして、この1カ月、思ったことを、その場で言葉にすることを心がけていました。 日々の中で気になったことをその場で伝えたり、係の中でもこどもの意見を尊重しながらも、自分の意見も伝えるようにしていました。 意識した分、言葉数は増えたが、一方であまり伝わっていないことを知りました。 例えば、こどもに対し、怒りの感情を伝えたことが数回あったが、肝心のこどもたちから、「全然怒らないよね」と言われ、私の伝え方では伝わっていなかったという気づきがありました。確かに、あまり感情的になっては、怒っている理由や今後どうしてほしいのか、という部分がわかりづらいのではないかと思い、冷静に伝えるように心がけていました。それが、受け取る側にとっては、怒りではなく、注意されたという認識になっていたのかもしれないと気づきました。 11月、もし自分の意見を伝える場面があれば、感情的になりすぎないよう、けれど相手に自分が本当に伝えたいことが伝わることを心がけたいと思います。 |
||
□ 研修担当のりのふりかえり 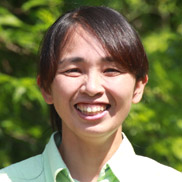 11月頭に開催される「だいだらぼっち祭り」に向けて、大人もこどもも10月は大忙しでした。
11月頭に開催される「だいだらぼっち祭り」に向けて、大人もこどもも10月は大忙しでした。そんな中、かんぽんも一緒に祭りを作り上げる仲間としての達成感を味わいつつも、仲間であるこどもたちへのアプローチや自分の役割、スタッフとしての支え方について迷い悩んだところのあった月だったように思います。 サポートする大人として、時には先回りして準備や配慮をしてあげることもあれば、一緒に悩みながらも作りあげていくこともあるでしょう。また、こどもたちが自力で解決するまで待つこともあるでしょう。 いずれにしても、あきらめずに向き合っていって欲しいと思います。苦しい時は周りを頼りにしてほしいと思います。そんな大人の姿を見て、こどもたちは目に見える、成果の見えやすいものだけでなく、成果の見えにくいもの、例えば人との関係性などを作ることにもあきらめないことや仲間に思いをぶつけることを学んでいくのではないでしょうか? そして、一緒に場を作っていく仲間として、大人であるとかこどもであるとかではない関係性を作っていくには日々の暮らしの積み重ねが大切なんだと感じられたかなぽん。 日々の暮らしを大切にしながら11月の祭りに向けて、かなぽんらしい持ち前の明るさと、ひとつひとつ、一人ひとりに丁寧に向き合う誠実さで乗り越えて行ってほしいと思います。頑張ってください! |
||
| 9月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
話し合い 9月は話し合いの多い月でした。主に11月にあるだいだらぼっち祭りの話、2学期になって改めて暮らしのことを話し合いました。 話し合いを重ねるうち、気になることが出てきました。話し合いに参加できている子とそうでない子がいること。テーマによって挙手の数に差があることです。 全体的に、わかりやすく、正解があるように見えるテーマの時、だいだらぼっち祭りの係決めやスケジュール決めなどは、よく手が挙がる気がしましたが、自分でしっかり考える場では、挙がる手は減っていました。心ここにあらずな子もいましたが、発言する何人かの意見でその場は進んでいく。みんなそれを待っているようにも見えました。 ただ、発言しない子も、実は考えていることもあります。だいだらぼっち祭りのテーマを決める時、そのテーマを選んだ理由を順に発表しました。普段、挙手しない子もしっかり自分の意見を言っていました。いつもの話し合いの様子ではわかりませんでしたが、しっかり考えていることが伝わってきました。どうすれば、こういう子の考えを話し合いで拾えるのだろうと感じました。 逆に、発言はするが本当に考えているのか?と思うこともあります。 生活面の話し合いで、「意識しよう」「みんなで気をつけよう」等の発言をした子たちの行動が変わらないのを目にし、やるせない気持ちになった。連絡や話し合いで、その場をやり過ごすために、とりあえず意見を言っただけのように感じてしまう時もありました。 これらをどうしたらいいのか考えました  話し合いそのもののやり方を見直してもよいのではないか。 話し合いそのもののやり方を見直してもよいのではないか。だいだらぼっちの話し合いでは全員が輪のように顔を突き合わせて話し合いをします。このような形は、人数の多さを感じる形でもあり、1人1人の当事者意識が薄れてるように思います。 その解消のために、例えば全員で話し合う前に、少人数のグループで話合う時間を設け、出た意見を全体でまとめていく方法もよいと思います。また、司会、書記、ノート記録係についても、再考の余地があると思いました。それは話し合いの度、係を決めるのに時間を使うのです。1回1回は数分でも、その数分で集中力を欠く子がいるし、挙手制ゆえの偏りもあります。また、話し合いにおいて、司会の存在は大きいと思います。現状では、面倒くさそうな口調や態度もしばしばあり、みな同じような進行をする時もあります。司会次第で話し合いは変わる。話し合いの議題をどう提示するか、誰から指名していくかなど係としてのテクニックはもちろんですが雰囲気をつくっていくという意味でも重要な役割だと思いました。ただ、こどもたちから話し合いについて、何か意見が出たことはない。問題意識がない中で、わざわざ変えていくように働きかけることがいいことなのか悩みます。何かを変えるためには、本人たちに問題意識があることが重要だと思いました。 実行委員  9月はこどもたちと二つの実行委員をやりました。お月見係はうまくいきましたが、読書パーティー係は悔いが残る結果でした。うまくいったり、うまくいかず悔いが残ることもありました。二つの実行委員をやって、見えてきたことがあります。 9月はこどもたちと二つの実行委員をやりました。お月見係はうまくいきましたが、読書パーティー係は悔いが残る結果でした。うまくいったり、うまくいかず悔いが残ることもありました。二つの実行委員をやって、見えてきたことがあります。こどもと2人でやった係は不安もありましたが、始まってみると2人だからこそうまく行った点も多かったのです。相談する時間を確保しやすいこと、2人の意見をまとめればよいので、早い段階でコンセプトが決まり、やることも見えました。私自身は作業の進行と、体調のコンディションを気にして、疲れているようであれば休憩をとる、気持ちが盛り上がるように声をかけるなどのフォローがしやすかったです。 当日には天候不良で急なプログラム変更もありましたが、細かい段取りまでしっかりとれていたことで、臨機応変に対応できました。 もう一つの係はこどもたちのなかに温度差があって、その温度差はそのまま係の話し合いにも表れてしまい、良い雰囲気を作ることができませんでした。熱量の高い子が同時期に他の係で忙しかったこともあり、3人揃う時間が取りにくく、私ともう1人の子で作業を進める段取りを取っていましたが、それもうまく気分をのせられず、ほとんど出来ませんでした。その準備不足はそのまま当日表れ、全員の意思疎通不足で全体の雰囲気を作っていくことができませんでした。 うまくいった係では、どんな雰囲気を作りたいか、そのために何をするかを話し合っていたけれど、一方の係では、そこを詰め切れなかった。それが当日、それぞれがどこに座るか、だれが何を話すのかなどの細かい段取り不足にも繋がっていたと思います。 10月に向けて  10月の振り返りをして、なぜ色々思っていることを心の中に留めておいて、声に出していかないのか、という話になりました。全員の前で話し、全体化しなかったのは、どうせ1人1人には他人事になってしまうだろうという、諦めが自分の中にあったからだと思います。でも諦めきれない自分もいて、個別に話をすることもありました。ただ、同時に響かなかったなという手ごたえの無さも感じていました。 10月の振り返りをして、なぜ色々思っていることを心の中に留めておいて、声に出していかないのか、という話になりました。全員の前で話し、全体化しなかったのは、どうせ1人1人には他人事になってしまうだろうという、諦めが自分の中にあったからだと思います。でも諦めきれない自分もいて、個別に話をすることもありました。ただ、同時に響かなかったなという手ごたえの無さも感じていました。私はどうしたいのか。本当は伝えたいと思っている自分がいる。ただ、次の予定が気になって手を挙げられなかったり、うまく言葉に表せなかったりする。 いとの話を聴いて、タイミングを逃さないことの重要性に気が付きました。うまくまとまってから話そうと思うと、こどもたちの心も暮らしも待ってくれません。誰かの話で「こどもの学びが生まれた瞬間を逃さず、拾い上げることでよい活動になる。そのためには、自分が深く理解し、こどもの学びの瞬間を見逃さない目、発言を聞き逃さない耳を備えていることが求められる。」という言葉を思い出しました。その目と耳を敏感にしたいと思いました。伝えたいことを、よりわかりやすく伝えることが重要だと思いました。 しかし、具体的に何をしたらよいのか。もやっとした瞬間を逃さないためには、その場で違和感をうまく言葉にしなければなりません。それが難しい。咄嗟に言葉が出るように訓練が必要なのだと思います。日常的に口数を多く、意識的に言葉の引き出しを増やし、言葉が口から出るまでにかかる時間を短くしていきたいと思います。 今度のだいだらぼっち祭りに向けて、劇の音響係と五平餅つくりの係になりました。前段の話の反省を踏まえ、どのように進めていくか考えるチャンスだと思います。音響はこどもと自分、1対1で、五平餅係は4対1なので、そこでも9月にもやもやしたことや、もっとこうすればよかったと思うことを活かせればと思っています。 |
||
□ 研修担当いとのふりかえり  1学期を経て、友達以上家族未満の関係性の中で、暮らしが始まったこどもたち。距離が近い分思っていることを言い合える子もいれば、他の子に対してはまだまだ遠慮してしまう子もいる中で、自分の思っていることを少しずつ伝えあうことにみんながチャレンジしたひと月だったのではないかと思います。かなぽんも自分の気持ちを伝えて良いのかと、悩みを抱えていました。何度も体当たりで気持ちをまっすぐ伝え続けても、こどもたちにはなかなか届いている気がしません。そうした中で諦めのような気持ちを抱いたかなぽんは、真剣に向き合っているからこそ苦しかったのではないかと思います。こどもたちも、自分の素直な気持ちを言うことで「嫌われないか」「みんなにどう思われるんだろう」「言っても伝わるのかな」など不安があったのではないでしょうか。素直な気持ちを伝えることは、実はとても勇気がいることなのです。距離が縮んだからこそ、どこまで踏み込んで良いのかわからない距離感の中で、こどもたちは繰り返し気持ちを伝えあい、本当に自分の思ったことを伝えあえる仲になっていくのではないかと思います。1年間の中盤を迎える2学期。臆せず根気よく、こどもたちに自分の気持ちを伝える後ろ姿を見せていってほしいと思います。 1学期を経て、友達以上家族未満の関係性の中で、暮らしが始まったこどもたち。距離が近い分思っていることを言い合える子もいれば、他の子に対してはまだまだ遠慮してしまう子もいる中で、自分の思っていることを少しずつ伝えあうことにみんながチャレンジしたひと月だったのではないかと思います。かなぽんも自分の気持ちを伝えて良いのかと、悩みを抱えていました。何度も体当たりで気持ちをまっすぐ伝え続けても、こどもたちにはなかなか届いている気がしません。そうした中で諦めのような気持ちを抱いたかなぽんは、真剣に向き合っているからこそ苦しかったのではないかと思います。こどもたちも、自分の素直な気持ちを言うことで「嫌われないか」「みんなにどう思われるんだろう」「言っても伝わるのかな」など不安があったのではないでしょうか。素直な気持ちを伝えることは、実はとても勇気がいることなのです。距離が縮んだからこそ、どこまで踏み込んで良いのかわからない距離感の中で、こどもたちは繰り返し気持ちを伝えあい、本当に自分の思ったことを伝えあえる仲になっていくのではないかと思います。1年間の中盤を迎える2学期。臆せず根気よく、こどもたちに自分の気持ちを伝える後ろ姿を見せていってほしいと思います。 |
||
| 7月・8月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
夏キャンプを経験して  夏のキャンプに本部スタッフとして参加して、相談員として参加していたときとは異なる経験ができました。 夏のキャンプに本部スタッフとして参加して、相談員として参加していたときとは異なる経験ができました。相談員として、族のこどもたちと関わっているときは、こどもへの言葉かけや族の関係性の中で、こどもに目に見える変化が表れ、その変化を受け止めることで自分自身の気づきや成長がありました。 今回、今までとは違う本部スタッフという立場になり、まずは自分に与えられた役割を果たし、そこから周囲をよく見て、相談員さんやこどもたちとコミュニケーションをとりたいと思っていました。自分のことに精一杯という場面も多々ありました。ひとつひとつ丁寧に行えば上手くいくという側面と、複数のことを同時並行で進めるべきという側面をうまく両立させることが自分の課題だと感じました。二つの事を同時に処理することの難しさを実感できたのは、キャンプの現場が常に臨機応変を求められていたからです。やるべきことに優先順位をつける、常に一歩先を考えて動く、その中でこどもや相談員さんとコミュニケーションをとるというのが理想であり、自分自身の目標でもありました。しかし、実際にはうまく行かない部分も多々ありました。 人とかかわること  キャンプが始まる前、こんなにたくさんの人と出会う夏はめったにない、この機会を大事に、たくさんの人から刺激を受けたいと考えていたけれど、実際に始まってみるとそんな余裕はありませんでした。相談員さんと一緒に作業する場面があり、コミュニケーションをとるのに最適であったにもかかわらず、自分でも驚くほど、ほとんど無言で過ごしてしまった時間がありました。これからの段取りや作業分担などを考えることに必死で会話に割くエネルギーが自分の中に残っていませんでした。自分に余裕がないと、人と向き合うことは本当に大変なことだと実感した出来事でした。 キャンプが始まる前、こんなにたくさんの人と出会う夏はめったにない、この機会を大事に、たくさんの人から刺激を受けたいと考えていたけれど、実際に始まってみるとそんな余裕はありませんでした。相談員さんと一緒に作業する場面があり、コミュニケーションをとるのに最適であったにもかかわらず、自分でも驚くほど、ほとんど無言で過ごしてしまった時間がありました。これからの段取りや作業分担などを考えることに必死で会話に割くエネルギーが自分の中に残っていませんでした。自分に余裕がないと、人と向き合うことは本当に大変なことだと実感した出来事でした。だいだらぼっちでこどもたちと過ごす中でも、人間関係が与える影響の大きさを感じていました。誰かが落ち込んでいると周りの子の心理状態にも影響するし、誰かの喧嘩が全く関係ない子に影響を与えていることもありました。私を含めこどもたちみんな、互いの良いところも悪いところも見ています。一緒に暮らす仲間の存在は、無意識だろうと意識していようと、自分のその時々の在り方に変化をもたらす大きな要因なのだろうと思いました。 山賊キャンプで、自分が族に入っていたときには、他の族の様子はほとんどわかりませんでした。しかし、本部スタッフという族から離れた立場になると、族ごとの雰囲気の違いや相談員さんの様子なども見ることができました。その中で、相談員さんの関わり方によってこどもの態度も変わってくることに気が付きました。特に族全体の雰囲気は相談員さんが担うところも大きいと感じました。声の大きさ、話を聴くときの相槌、他の子への接し方など、自然とこどものロールモデルになっているようでした。 誰かと時間を過ごすとき、自分自身がどのように過ごすかというのは、一緒に過ごした時間の長さに関わらず、相手にある程度の影響を与えるようだとわかりました。だいだらぼっちで1年間という長い時間を共にしたら、その相互作用の先にはなにが待っているのだろう、と楽しみになりました。 だいだらぼっちの7月と8月  キャンプとだいだらぼっちの違いを大きく感じたのは、こどもの変わり方です。キャンプでは、こどもと過ごす短い期間の間に、子どもたちの行動という目に見える変化を感じていました。片付けをさぼっていた子が自分から動くようになった、消極的な子が自分からチャレンジした、などわかりやすい変化です。だいだらぼっちでは、暮らしがベースになっているので、そのようなわかりやすい行動の変化を感じることはあまりないと感じています。その分、ふとした瞬間に内面の変化を感じることがあります。仲間への声掛けや、前向きな発言などです。内面の変化が目に見える変化として表れているのかなと思います。 キャンプとだいだらぼっちの違いを大きく感じたのは、こどもの変わり方です。キャンプでは、こどもと過ごす短い期間の間に、子どもたちの行動という目に見える変化を感じていました。片付けをさぼっていた子が自分から動くようになった、消極的な子が自分からチャレンジした、などわかりやすい変化です。だいだらぼっちでは、暮らしがベースになっているので、そのようなわかりやすい行動の変化を感じることはあまりないと感じています。その分、ふとした瞬間に内面の変化を感じることがあります。仲間への声掛けや、前向きな発言などです。内面の変化が目に見える変化として表れているのかなと思います。7月、暮らしの中で感じていることや、これからもっと仲間になっていくためにどうしたらいいかという話し合いを繰り返しました。その中で言葉遣いについて多くの意見がありました。人からかけられた言葉は、いい方にも悪い方にも大きく働くことをみんなが日々の中で感じていたことがわかりました。 言葉にはその人の内面の状態が反映されていると思います。 1学期の振り返りでは、今のだいだらのいいところ、改善点を出し合いました。また、自分がしてもらって嬉しいこと、できればやめてほしいことも一人ずつ発表しました。気になったのは、こしょこしょ話が嫌だ、という人が多かったことです。みんなが嫌だと思っているのに、している人がいる。自分の目の前でされたらいやなのに、気が付いたら自分もやってしまっている、、ということがあるのかなと思いました。誰かの不安定につられて、自分も不安定になる、不安定はこしょこしょ話や言葉使いなどの行動となって表れる、それがまた誰かに影響するという繰り返しのように感じました。 内面が気持ちや行動に影響するなら、言葉や行動も内面に影響するのではないかと思います。 2学期に向けて  キャンプ中、自分にできることとして、できるだけプラスで前向きな言葉を使おう、と目標立てていました。ネガティブな言葉は気持ちもネガティブになるだけでなく、周りの人もマイナスな気持ちに巻き込んでしまうと考えたからです。実際、意識的にポジティブな言葉を使うことで、最後まで前向きな気持ちで取り組むことができました。想定外の事に対して、笑ってどうにか乗り越えようとするのと、大変だ、どうにかしようと暗く受け止めるのとでは、同じ結果でも事象に対する印象は大きく変わると思います。 キャンプ中、自分にできることとして、できるだけプラスで前向きな言葉を使おう、と目標立てていました。ネガティブな言葉は気持ちもネガティブになるだけでなく、周りの人もマイナスな気持ちに巻き込んでしまうと考えたからです。実際、意識的にポジティブな言葉を使うことで、最後まで前向きな気持ちで取り組むことができました。想定外の事に対して、笑ってどうにか乗り越えようとするのと、大変だ、どうにかしようと暗く受け止めるのとでは、同じ結果でも事象に対する印象は大きく変わると思います。2学期が始まってこどもたちと過ごす日々の中で、いろいろなことがあると思います。まずは、意識的に前向きな、でも自分に素直な言葉を使っていきたいです。 |
||
□ 研修担当くみのふりかえり  だいだらぼっちが夏休みの間、グリーンウッドでは「夏の信州こども山賊キャンプ」が開催されます。約1000人のこどもたちと約300人のボランティアが泰阜村へ集まる、激動の夏休みです。 だいだらぼっちが夏休みの間、グリーンウッドでは「夏の信州こども山賊キャンプ」が開催されます。約1000人のこどもたちと約300人のボランティアが泰阜村へ集まる、激動の夏休みです。かなぽんにはキャンプの運営に深く関わる、本部スタッフとして参加してもらいました。本部スタッフは、参加者であるこどもたちや相談員(ボランティア)さんと共にキャンプをつくることはもちろん、食材や道具の準備をしたり、けがや病気をしたこどもをみたりするなどの、淡々とした準備と臨機応変さも求められます。 かなぽんは本部スタッフをやってみて、「自分の役割に必死で、思った以上に参加者とコミュニケーションを取れていなかった」、「同時並行で、臨機応変に進めることが課題だと感じた」と話していました。 かなぽんは、日頃から“段取り”をしっかりと考えながら過ごすひとだなぁと感じていましたが、良い意味で先を読むことができない“キャンプ”、“こども”を相手にすると、自分が考えていた段取りから外れてしまうこともあったのだと思います。 起こりうることを考え、準備しておく力は非常に大切ですが、想定外のことが起こったときに、優先順位を考え行動する力、またそれを楽しむ力も、生きる上で非常に大切だと感じます。ぜひそんな力を、だいだらぼっちのこどもたちと(そして私も)一緒に学び合えたらと思います。 2学期に向けて、「前向きな、でも自分に素直な言葉を使っていきたい」と語ったかなぽん。ひとは一緒に過ごすひとの行動や気持ちにとても左右されたり、新しいことを気づかされたりします。相手がこどもであろう大人であろうと関係ありません。2学期の、かなぽんの“素直な言葉”を楽しみにしています。 |
||
| 6月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
6月を過ごして  6月は自分自身の立場を考えることが多い月でした。 6月は自分自身の立場を考えることが多い月でした。こどもと接している時、キャンプに向けて研修をしている時。組織や集団の中で自分はどういう位置にいるのだろうと考えました。 だいだらぼっちで過ごす日々の中で、相談員として、こどもたちとの関係性も少しずつ築けてきたのかなと感じていました。その中で、大人とこども、相談員とこども、という言葉がこどもの口から出てきたことがありました。その言葉を聴いて、私は大人、相談員として見られているんだと自覚すると同時に、こどもたちが、年齢が近いせいか、私のことをこどもに近いと感じていることを知りました。それだけが理由なのか分かりませんし、関係性ができてきたからかもしれませんが、学校での出来事や様々な悩み等を聴く機会も多くなってきたように思えます。しかし、相談員という立場である以上、まるで友達のような関係性でいいのだろうかと考えました。そう考えたのは、相談員という名前にある通り、子どもの相談を聴いて一緒に悩んだり、やりたいことをどうしたら実現できるか一緒に考えたりする相談相手であったほうがいいと思ったからです。友達でも同じことができますが、一緒に楽しむだけでなく、危ないことは注意するなどの責任がある点が、大きな違いなのではないかと思いました。 これまでは、一緒に暮らす仲間という気持ちで、あまり接し方を意識したことはありませんでした。言おうと思ったことがあったら、きちんと伝わる言葉にするということは意識的にやっていたつもりでしたが、そのやり取りの中で、相手と自分の距離感という視点はほとんど気にしていなかったなと思いました。伝わるように意識するあまり、話し方や言葉使いが友だちに対して話しているようになっていたかもしれません。こどもたちとは、一緒に暮らしをつくる仲間であるけれど、相談員とこどもという違う立場でもあります。その距離感をどうしたらいいだろうと悩みましたが、自分自身の立場を客観視できたことで、接し方や距離感よりも、私がどういう心持で向き合うかのほうが重要だと思うようになりました。友達のような距離感であったとしても、その関係性だからこそ伝えられることもあると思います。私自身が自分の立場についてしっかり心にとめておければ、接し方や距離感など、見えるところの形は今のままで、自分らしく頑張ろうと思いました。 夏のキャンプに向けて  川研修が始まり、新しいことの連続でした。山賊キャンプに向けてたくさんのことが動きだしていて、相談員として参加している時は想像もしなかったことがたくさんあります。安全や衛生を保つことと、こどもがやりたいことを思いっきり楽しめるようにすることを両立させるためには、事前にできる限り多くのパターンを想定し、一つ一つのリスクに敏感になっておくことが必要だと分かりました。山賊キャンプという規模の大きいことを動かすために、組織がどのように役割を分担しているのか、1カ月と少しのためにどれくらい前から準備をしているのかなど、今まではキャンプでこどもと関わることや自分のチャレンジによって成長できる場であると感じているだけでしたが、仕事として活動を見る視点が得られたと思います。キャンプに向けての動きや、並行して色々な事業が動いていく様子を見られること、そこで発生する仕事に対して誰がどのように関わっていくのかを知ることができました。 川研修が始まり、新しいことの連続でした。山賊キャンプに向けてたくさんのことが動きだしていて、相談員として参加している時は想像もしなかったことがたくさんあります。安全や衛生を保つことと、こどもがやりたいことを思いっきり楽しめるようにすることを両立させるためには、事前にできる限り多くのパターンを想定し、一つ一つのリスクに敏感になっておくことが必要だと分かりました。山賊キャンプという規模の大きいことを動かすために、組織がどのように役割を分担しているのか、1カ月と少しのためにどれくらい前から準備をしているのかなど、今まではキャンプでこどもと関わることや自分のチャレンジによって成長できる場であると感じているだけでしたが、仕事として活動を見る視点が得られたと思います。キャンプに向けての動きや、並行して色々な事業が動いていく様子を見られること、そこで発生する仕事に対して誰がどのように関わっていくのかを知ることができました。教師を目指しているので、教師という仕事が社会からどのように見られているのだろうということに関心があるのですが、よく言われることが、教師は社会を知らない、ということです。大学を卒業してすぐに学校に勤めたら、学校という狭いところしか知らないということも確かにあると思います。しかし、本当にそれでいいのだろうかという思いもあります。通っている子どもたちにとって、学校は大きな社会だろうと思うからです。そこにいる大人が学校しか知らない、教師という仕事しか知らないでいることは、子こもたちの世界を狭めいているのではないかと思っていました。今回、今まで知らなかった裏側を見ることができて、自分の知っている世界を少し広げられました。自分の世界が広がれば、受け止められることの幅も広く深くなり、こどもに見せられる世界も広がると思います。広い世界を自分の中に持てるよう、今後も色々な事を知っていきたいです。  一方で、だいだらぼっちとしては6月は4月5月と比べて大きな予定がなく、やりたいことにチャレンジする時間がたくさんありました。 一方で、だいだらぼっちとしては6月は4月5月と比べて大きな予定がなく、やりたいことにチャレンジする時間がたくさんありました。ふと何人かの子とプリンが食べたい、という話になって、早速時間のある休日に作ることになりました。ところが、きちんと段取りをとらなかったので、作る直前になって材料を使ってもいいか、みんなに確認することになりました。実はその日の朝に牛乳をたくさん使っていたので、飲む分がなくなってしまうかもしれないと思ったのです。その時、人数分作るのに必要な材料を使うのではなく、使える分の材料で作ってみんなで分ければいい、という意見がでました。結果として使える材料で全員分の美味しいプリンができあがり良い休日になったのですが、事前の段取りがどうして必要なのかを再認識する出来事でした。この場合、予め牛乳を多めに発注してもらったり、作りたい数日前からみんなに相談して牛乳をとっておいてもらうなど、方法はいくつもあったなと思いました。 段取りの必要性を感じたことがもう一つあります。 6月にやりたいこととして、自分から何か発信できたらいいなと考えていました。どんな内容にするか、どんな形式がいいのか、と色々と考えて、けれど実際に形にする時間を上手く作れず、構想を練っただけで終わってしまいました。段取りをとるということは、何をしたいか、どのようにするのかを考えるだけでなく、何をいつまでにやらなければいけないのか、時間の見通しを持って計画することに意味があると感じました。 |
||
□ 研修担当いっちーのふりかえり  6月当初に担当として話をして感じたことは、仕事もこどもたちとの日常も真摯に向き合っているということ。そして、その日常の中で様々なことを感じているということでした。ですが、言葉の中に曖昧なものも多く、自分の気持を整理したり、なぜそう思ったのかということを突き詰めたりする時間が足りていないように感じました。そのため6月は、暮らしの中で感じたモヤモヤを書き出して、なぜそう感じたのかを突き詰めるという事をしてもらいました。 6月当初に担当として話をして感じたことは、仕事もこどもたちとの日常も真摯に向き合っているということ。そして、その日常の中で様々なことを感じているということでした。ですが、言葉の中に曖昧なものも多く、自分の気持を整理したり、なぜそう思ったのかということを突き詰めたりする時間が足りていないように感じました。そのため6月は、暮らしの中で感じたモヤモヤを書き出して、なぜそう感じたのかを突き詰めるという事をしてもらいました。かなぽんの育成プロジェクトに参加した理由は、自分の心や体で感じたこと、頭と心の両方が納得した言葉を話せるようになりたいということでした。その目的に対して、自分の気持ちに深く向き合い突き詰めるということは、必要不可欠なことです。そうして向き合い続けたからこそ、こどもたちとの関係性や、仕事としての視点、段取りの大切さのような今までの日常でもあったはずのことに改めて気づけたのだと思います。 かなぽんが来てからだいぶ経つような気もしますが、まだたったの3ヶ月。今後も様々な経験をして視点を増やし、自分の気持と深く向き合い言葉にしていくということを続けて欲しいと思います。 |
||
| 5月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
5月を過ごして  5月は4月に感じた、「もっとこうすればよかった」を少しでも減らせるようにしようと意識して過ごしました。思ったことを伝えることは、本当にいいのかなと二の足を踏むことも多々ありました。それでも、自分がこうした方がいいなと思ったことは、素直に行動に移すように心がけました。そうすることで自分の考えや感情を言葉で表す機会が増え、言葉にすることで自分でもよくわかっていなかった部分に気が付くこともありました。 5月は4月に感じた、「もっとこうすればよかった」を少しでも減らせるようにしようと意識して過ごしました。思ったことを伝えることは、本当にいいのかなと二の足を踏むことも多々ありました。それでも、自分がこうした方がいいなと思ったことは、素直に行動に移すように心がけました。そうすることで自分の考えや感情を言葉で表す機会が増え、言葉にすることで自分でもよくわかっていなかった部分に気が付くこともありました。こどもたちは、暮らしに慣れてきたところで人間関係の悩みなども出て来ていました。その中で、こどもが悩んでいることが、些細なすれ違いが原因だったり、私から見ると悩まなくてもいいのではないかと思うようなその子の思い込みだったりという場面もありました。こどもたちにとって学校やだいだらぼっちでの人間関係は生活の大きな部分を占めていて、その中で安心できる立ち位置を探すというのは、精神的な安定につながっているのだなと感じました。「友達と仲間は違う」と言っているこどもがいて、まさにその通りだなと思う反面、そう考えられるようになるまでは、自分はどこにいたらいいのかなと、どこかへの所属を求めて悩んでしまうのかなと思いました。どのようなきっかけで考え方が変わっていくのかを見ていきたいです。 田植えを経験して感じたこと  初めて田植えをしました。こどもたちと一緒にやった時は、水が濁っていて深く、真っ直ぐに植えることが難しい状態でした。何よりも驚いたのは、土に足をとられる感覚です。土があんなに柔らかく、まとわりついてくるような質感を体験したのは、初めてのことでした。長靴を履いて作業したのですが、足を持ち上げようとすると、長靴が田んぼにはまり、何度も足だけが抜けてしまいました。まず、踵を持ち上げて、ゆっくりと力を加えながら足全体を持ち上げていくと抜けると教えてもらい、試してみると、確かにうまく足を抜くことができました。田植えと聞いてイメージしていたことと、実際にやってみるのとでは大きく違いました。腰が痛くなるかな、暑くて大変なのかなと思っていましたが、本当に大変なのは、足が上手く動かないこと、みんなで息を揃えることでした。横一列になると、自分の近くの人の様子はよくわかるけれど、少し離れている人は死角になり、ほとんど見えませんでした。一番端にいる人は、離れている分、かえってよく見ることができ、その様子が集団生活に似ているなと思いました。自分の一番近くにいる人のことは、よく見え、離れている人のことは客観的に見ることができるけれど、近くも遠くもない人のことは分かったつもりでも分かっていないことや、見ているつもりでも見えていないことがあるのではないかなと思います。 初めて田植えをしました。こどもたちと一緒にやった時は、水が濁っていて深く、真っ直ぐに植えることが難しい状態でした。何よりも驚いたのは、土に足をとられる感覚です。土があんなに柔らかく、まとわりついてくるような質感を体験したのは、初めてのことでした。長靴を履いて作業したのですが、足を持ち上げようとすると、長靴が田んぼにはまり、何度も足だけが抜けてしまいました。まず、踵を持ち上げて、ゆっくりと力を加えながら足全体を持ち上げていくと抜けると教えてもらい、試してみると、確かにうまく足を抜くことができました。田植えと聞いてイメージしていたことと、実際にやってみるのとでは大きく違いました。腰が痛くなるかな、暑くて大変なのかなと思っていましたが、本当に大変なのは、足が上手く動かないこと、みんなで息を揃えることでした。横一列になると、自分の近くの人の様子はよくわかるけれど、少し離れている人は死角になり、ほとんど見えませんでした。一番端にいる人は、離れている分、かえってよく見ることができ、その様子が集団生活に似ているなと思いました。自分の一番近くにいる人のことは、よく見え、離れている人のことは客観的に見ることができるけれど、近くも遠くもない人のことは分かったつもりでも分かっていないことや、見ているつもりでも見えていないことがあるのではないかなと思います。 その後、大人が管理する田んぼの田植えもしました。手で植えるのではなく、手押しの田植え機で植えていく作業でした。手で植える大変さを感じてからだったので、大変な作業を効率化するためにいろいろな工夫が重ねられていることを実感できました。ただ押すだけでなく、列が等間隔になるようにすること、一定のスピードで進むことなど、気をつけることがたくさんあり、実際にやってみるとその難しさが分かりました。農家では田植えは一人前になるまでなかなか任せてもらえないという話を聞いて、この作業にはこの先1年間の暮らしがかかっているという重みを感じました。この日は裸足で田んぼに入りました。長靴で入った時は動きにくいとばかり思っていたけど、裸足で入ると、土がふかふかしていることや、水面にいるアメンボなどに目が向きました。何事も自分の身体で感じると、頭で分かる以上のことを得られるなと実感しました。 その後、大人が管理する田んぼの田植えもしました。手で植えるのではなく、手押しの田植え機で植えていく作業でした。手で植える大変さを感じてからだったので、大変な作業を効率化するためにいろいろな工夫が重ねられていることを実感できました。ただ押すだけでなく、列が等間隔になるようにすること、一定のスピードで進むことなど、気をつけることがたくさんあり、実際にやってみるとその難しさが分かりました。農家では田植えは一人前になるまでなかなか任せてもらえないという話を聞いて、この作業にはこの先1年間の暮らしがかかっているという重みを感じました。この日は裸足で田んぼに入りました。長靴で入った時は動きにくいとばかり思っていたけど、裸足で入ると、土がふかふかしていることや、水面にいるアメンボなどに目が向きました。何事も自分の身体で感じると、頭で分かる以上のことを得られるなと実感しました。4月、5月と過ごしてみて、目の前にあることや与えられることに取り組んだり、初めてのことに挑戦してみたりすることが多かったなと感じます。その中で、暮らしをもっとよくするために自分には何ができるのだろうと考えることもありました、6月は、自分にできることや、自分の視点から思っていること、こうしたらもっとよくなるのではないかということを発信できたらいいなと思います。 |
||
□ 研修担当ぱるのふりかえり  新しい環境になって少したった頃の5月は、人は不安定になりやすいものです。それはこどもはもちろん、大人も同じ。かなぽんも全く異なる暮らしが始まって間もなく、色々悩んだりしたこともあったかと思います。それでも、4月のふりかえりを踏まえてこうした方がいい、という自分の想いをしっかり相手に伝えたり、悩んでいる目の前のこどもの様子を冷静に分析したりするなど、この2か月でかなぽんなりの視点と姿勢が養われたのではないかと思います。 新しい環境になって少したった頃の5月は、人は不安定になりやすいものです。それはこどもはもちろん、大人も同じ。かなぽんも全く異なる暮らしが始まって間もなく、色々悩んだりしたこともあったかと思います。それでも、4月のふりかえりを踏まえてこうした方がいい、という自分の想いをしっかり相手に伝えたり、悩んでいる目の前のこどもの様子を冷静に分析したりするなど、この2か月でかなぽんなりの視点と姿勢が養われたのではないかと思います。こどもと向き合うとき、こどもの「今」の気持ちに寄り添うことはとても大切です。しかし一方で、今目の前の現象だけにとらわれない視点もとても重要。泣いたり、悩んだり、暴れたりとわかりやすいメッセージを発信しているこどもに周囲は目を向けがちですが、見えていないところに問題の本質があったり、メッセージを発していないこどもが問題をかかえていたりするものです。全体を俯瞰的に見て、対応していくことの大切さに気付き、言葉にできているかなぽん。しかも、自然とのふれあいからもこの大切な視点を発見していて、実感から湧き出た納得の気づきなのだろうと思います。日々めまぐるしく起こる色々な事に、どう考え、どう行動していくのか?日々学びですね!応援してます、かなぽん! |
||
| 4月育成プロジェクトかなぽん研修報告 | ||
はじめに  私がだいだらぼっちに来ることを決めたのは、自分自身の足りない所を変えたいと思ったからです。教職を目指し、大学で3年間学び、教育実習を経験する中で、「言葉」というものを意識するようになりました。自分の心の中で考えていることと発する言葉に齟齬が生じたときや、その場に適した言葉を話していて、内容に偽りがなくても、私の中に落とし込まれていない、上滑りするような言葉を話していることが多々あることが、とても気になったのです。 私がだいだらぼっちに来ることを決めたのは、自分自身の足りない所を変えたいと思ったからです。教職を目指し、大学で3年間学び、教育実習を経験する中で、「言葉」というものを意識するようになりました。自分の心の中で考えていることと発する言葉に齟齬が生じたときや、その場に適した言葉を話していて、内容に偽りがなくても、私の中に落とし込まれていない、上滑りするような言葉を話していることが多々あることが、とても気になったのです。自分の心や身体で感じたこと、頭と心の両方が納得した言葉を話せるようになりたい、そう思いました。 そのように考えていたとき、頭に浮かんだのは、大学生になってから毎年夏に参加していた山賊キャンプでした。こどもたちが能動的に参加し、数日の間に目に見えて成長する姿を目の当たりにし、こどもたちが学ぶ姿の中に自らの学びがあると実感していました。そこでのこどもの学びは学校の教室のそれとは少し違うものでした。教科書の理解度が向上するようなものではありません。けれど、人と一緒に何かをやり遂げることや他人の意見に耳を傾けること、やりたいことのために準備をすることなど、勉強の土台、あるいは生きていく中で身に着けるべきことが、なぜ大切とされているのかを肌で感じることのできる場なのだと思いました。 私は、全力でぶつかるこどもたちの中では、表面だけを取り繕っていても仲間には慣れないと理屈ではなくわかっていたように思います。だから、キャンプに参加している時の私は、自分の言葉に自分でも納得できていたし、誰かに深く突っ込まれたとしても、相手が納得するように話せただろうと思います。 だいだらぼっちで1年間暮らすことで、キャンプで感じたことをより深め、自分のものにできるのではないかと考えました。また、キャンプとは違い、1年間という長い時間で、キャンプでは見ることのできないこどもの姿がみられるのではないかという思いもあります。暮らしを共にしていれば、相手の良いところだけを見ているわけにはいかないと思います。嫌な思いをしたとき、苦しい時、そのような時に自分はこどもとどのように関わるのか、自分の中で軸となる何かを見出したいです。 4月を過ごしてみて  だいだらぼっちで1カ月暮らしてみて、日々はめまぐるしく過ぎていきました。何かを頑張っても1カ月は過ぎるし、逆に何もしなくても時間は流れていくんだというのが、こどもたちを見ていて感じたことです。こどもたちは暮らしの中で様々な役割があります。役割を持つかどうかも自分で決められます。役割があって頑張れる子もいれば、自分のことで精一杯の子もいます。全員が頑張らなくてもまわってしまうからこそ、全員が能動的に暮らせるようになるにはどうしたらいいのだろうと思いました。無理に参加させたいわけではなく、やりたくないことや苦手な事から逃げることが、なぜよしとされないのか、どうしたらわかるのだろうかと考え、私自身にも納得のいく答えがない事に気が付きました。よく考えたらわかっていないのに、答えを持ち合わせている気になっていることが、他にもたくさんあるのだろうと思います。それが、中身のない言葉を生む理由のひとつなのだろうと思いました。 だいだらぼっちで1カ月暮らしてみて、日々はめまぐるしく過ぎていきました。何かを頑張っても1カ月は過ぎるし、逆に何もしなくても時間は流れていくんだというのが、こどもたちを見ていて感じたことです。こどもたちは暮らしの中で様々な役割があります。役割を持つかどうかも自分で決められます。役割があって頑張れる子もいれば、自分のことで精一杯の子もいます。全員が頑張らなくてもまわってしまうからこそ、全員が能動的に暮らせるようになるにはどうしたらいいのだろうと思いました。無理に参加させたいわけではなく、やりたくないことや苦手な事から逃げることが、なぜよしとされないのか、どうしたらわかるのだろうかと考え、私自身にも納得のいく答えがない事に気が付きました。よく考えたらわかっていないのに、答えを持ち合わせている気になっていることが、他にもたくさんあるのだろうと思います。それが、中身のない言葉を生む理由のひとつなのだろうと思いました。自分の課題は、問題にすぐに背を向けてしまうことだと感じました。今に始まったわけではなく、自分で気が付いたときには、物事に対し波風立てぬようにする癖が染みついてしまっていました。そのことを痛感したのは、こどもに対し、言いたいことがあった時に、同じことを2回までは言ったのに、3回目を言うことをやめてしまったときです。後で、なぜ3回目を言わなかったのだろう、言えなかったのだろうと考えました。また、トラブルがあって、きちんと話がしたいと思っていたのに、そのままにして時間が解決することを待ってしまったこともありました。なぜ、向き合えなかったのかを突き詰めていき、そのような自分を変えていきたいと思います。 だいだらぼっちでの暮らしは、みんなでつくっていくものだなと特に感じることはお風呂です。ガスのお風呂では寒ければ、追い焚きボタンを押します。だいだらぼっちの五右衛門風呂は、薪で焚くお風呂なので、放っておくと、お湯がどんどん冷めてしまいます。早く上がった人が、追加で薪をくべて火を焚く様子はまさに追い焚きで、当たり前に使っていた言葉は暮らしの中から生まれているんだなと感じる瞬間です。お風呂に入る時、上がってから、誰かが追い焚きしてくれているところを見ると、みんなで暮らしているということを実感します。 5月に向けて  4月を過ごした中で見えた課題を乗り越えるために、まずは何事にもチャレンジしていこうと思います。子どもたちとたくさん話をして、向き合っていくことはもちろん、苦手な事にも、積極的に取り組んでいきたいです。特に、食に関することは、頑張りたいと思います。私は偏食で好き嫌いが多く、料理もほとんどしたことがありませんでした。でも、だいだらぼっちでは、村の方から新鮮な野菜をいただくことも多く、食べることと生きることのつながりを感じるようになりました。こどもたちと一緒にご飯づくりをたくさんして、色々な食材を美味しいと味わえるようになりたいと思います。 4月を過ごした中で見えた課題を乗り越えるために、まずは何事にもチャレンジしていこうと思います。子どもたちとたくさん話をして、向き合っていくことはもちろん、苦手な事にも、積極的に取り組んでいきたいです。特に、食に関することは、頑張りたいと思います。私は偏食で好き嫌いが多く、料理もほとんどしたことがありませんでした。でも、だいだらぼっちでは、村の方から新鮮な野菜をいただくことも多く、食べることと生きることのつながりを感じるようになりました。こどもたちと一緒にご飯づくりをたくさんして、色々な食材を美味しいと味わえるようになりたいと思います。 |
||
□ 研修担当みけのふりかえり  怒涛のような一カ月を過ごしてみて、かなぽんが感じた自分への課題は「問題に背を向けてしまうこと」でした。が、かなぽんと一緒に過ごして感じたことは、決して背を向けてはいないということです。こどもたちの言動に「あれ?」と私が思う場面でかなぽんは必ず声をかけていました。ただ、「あと一歩、踏み出せばよかった」と思う場面が多かったのだと思います。 怒涛のような一カ月を過ごしてみて、かなぽんが感じた自分への課題は「問題に背を向けてしまうこと」でした。が、かなぽんと一緒に過ごして感じたことは、決して背を向けてはいないということです。こどもたちの言動に「あれ?」と私が思う場面でかなぽんは必ず声をかけていました。ただ、「あと一歩、踏み出せばよかった」と思う場面が多かったのだと思います。だいだらぼっちでは大人もこどもも等しく「一票」を持っています。暮らしをまわしていくために、何かを成し遂げるために、お互いを大切にするために、責任ある「一票」です。かなぽんが言うように、大勢で暮らしているだいだらぼっちでは、その「一票」を発動させなくても暮らしがまわっていってしまうこともあります。かなぽんが「何事にもチャレンジしよう!」と決めたことは、かなぽん自身が「能動的に=一票に責任を持って」暮らしていくための足掛かりとなると思います。そしてそれは「あと一歩」を踏み出すことにきっとつながるはず!この一年でかなぽんがどんなチャレンジをしていくのか楽しみです。がんばれ、かなぽん! |
||
| 育成プロジェクト TOP | ||
* 問い合わせ・連絡先 * 〒399−1801 長野県下伊那郡泰阜村6342-2 TEL:0260-25-2172 FAX:0260-25-2850 e-mail camp@greenwood.or.jp |
