| |
||
 |
||
|
||
| 3月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
引き継ぎ会  3月中旬、今年度のこどもたちから来年度新規で加わるこどもたちへ、だいだらぼっちの暮らしを伝える引き継ぎ会が終了しました。来年度のメンバーに本当に伝えたいことは何なのかを準備の段階から何度も話し合い、私も仲間の一人として、こどもたちと共にたくさん考えました。意見がぶつかったり、みんなの気持ちが引き継ぎ会へ向いていないのではないかと悩んだり、当日までの間、不安になることがたくさんありました。何度もみんなで話し合いを重ね、自分たちで作るという意識を確認しました。その後に行った前日の最終確認のときに私の目に映ったこどもたちの姿はとても落ち着いていて、覚悟が決まっているように思えました。そんなこどもたちの姿に後押しされて、私も自信を持って引き継ぎ会を迎えることができました。そして当日はこどもたちの想い溢れる最高の引き継ぎ会で、終わるんだという実感とともに涙が止まりませんでした。 3月中旬、今年度のこどもたちから来年度新規で加わるこどもたちへ、だいだらぼっちの暮らしを伝える引き継ぎ会が終了しました。来年度のメンバーに本当に伝えたいことは何なのかを準備の段階から何度も話し合い、私も仲間の一人として、こどもたちと共にたくさん考えました。意見がぶつかったり、みんなの気持ちが引き継ぎ会へ向いていないのではないかと悩んだり、当日までの間、不安になることがたくさんありました。何度もみんなで話し合いを重ね、自分たちで作るという意識を確認しました。その後に行った前日の最終確認のときに私の目に映ったこどもたちの姿はとても落ち着いていて、覚悟が決まっているように思えました。そんなこどもたちの姿に後押しされて、私も自信を持って引き継ぎ会を迎えることができました。そして当日はこどもたちの想い溢れる最高の引き継ぎ会で、終わるんだという実感とともに涙が止まりませんでした。引き継ぎ会の準備から当日までの間、こどもたちとたくさん話をしました。落ち着いてお互いの本音を言い合えた時間で、最後にこどもたちと1年間を振り返り、噛み締め、分かち合えたような気がします。本当にいい時間でした。 1年を振り返って  1年間で私という人間は大きく変わったと思います。ここに来たときはただ不安で自信もなくて自分の想いを素直に伝えることや、言い切ることができませんでした。でも、仲間や暮らし、豊かな自然、生き物、ものづくりなど、たくさんの出会いの中で揉まれ、悩み、学び、いつの間にか自分の中の大切なことが明確になり、自信を持ってそれを宣言することができるようになりました。 1年間で私という人間は大きく変わったと思います。ここに来たときはただ不安で自信もなくて自分の想いを素直に伝えることや、言い切ることができませんでした。でも、仲間や暮らし、豊かな自然、生き物、ものづくりなど、たくさんの出会いの中で揉まれ、悩み、学び、いつの間にか自分の中の大切なことが明確になり、自信を持ってそれを宣言することができるようになりました。私が学んだ“大切なこと”とは、健康第一、シンプルに考えること、行動で示すこと、こどもたちを信じること、下手でもいいから思いを言葉にして伝えることなど、ここには書ききれないくらいにたくさんあります。その中でも素直に謙虚に誠実にということはこれから生きていく上で人として忘れないでいたいと思えたことです。何かにぶつかったり、悩んだりしたときは、常にここに立ち返り、自分を見つめ直せる人間になりたいです。  そんなたくさんの大切なものが1年間かけてゆっくりと私の中に積み重なり、今の私が在ります。1年前には想像もつかなかった自分がいることにとても不思議な気分です。 そんなたくさんの大切なものが1年間かけてゆっくりと私の中に積み重なり、今の私が在ります。1年前には想像もつかなかった自分がいることにとても不思議な気分です。今、1年間を振り返ると支えられてばかりだったと感じます。ここで出会ったすべての人、モノのおかげで深い濃い1年が過ごせたと感じるとともに、ここに来るまでに私に関わってくれた人々や、家族がこんなにも私を支え、応援してくれていたのだと改めて気付くことができました。 だいだらぼっちで暮らせたことは本当に幸せでした。そんな幸せを謙虚に受け止めながら、感謝を忘れず、新たな地で頑張ります。1年間ありがとうございました。 |
||
□ 研修担当つぅのふりかえり  引き継ぎ会を終え、ここまでの出来事が徐々に実感としてまりおの頭と体に浸透していくような時期での振り返りでした。4月からだいだらぼっちのこどもたちと走りぬいた一年間。つまずいたり、悩んだりしながらも全力で3月まで来たと思います。こどもたちと向き合うことで信頼関係を築き上げ、3月の引き継ぎ会を作り上げたということは大きな財産になると思います。そこから何を学び、どう磨くのかはこれからのまりおにかかっていると思います。ここで感じたものを活かして、社会に羽ばたいていってほしいと願います。 引き継ぎ会を終え、ここまでの出来事が徐々に実感としてまりおの頭と体に浸透していくような時期での振り返りでした。4月からだいだらぼっちのこどもたちと走りぬいた一年間。つまずいたり、悩んだりしながらも全力で3月まで来たと思います。こどもたちと向き合うことで信頼関係を築き上げ、3月の引き継ぎ会を作り上げたということは大きな財産になると思います。そこから何を学び、どう磨くのかはこれからのまりおにかかっていると思います。ここで感じたものを活かして、社会に羽ばたいていってほしいと願います。一年間過ぎてしまえばあっという間の出来事だと思いますが、この一年での成長はこの仲間たちなしでは得られなかったものだと思います。ここでともに暮らしを作った仲間たちとの時間、たくさんの発見をくれた自然、どれも謙虚に受け止め大きく成長したと感じます。 一年間本当にこどもたちの良き相談相手になり、村民となり一緒に生活できたことを私たちも誇りに思うのと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。これからは社会人!ここでの経験を活かし、誰からも頼られる先生になってほしいです。がんばれまりお!! |
||
| 2月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
2回目の登り窯  2月、今年度2回目の登り窯を焚きました。今回私は、全体を見通し、こどもたちと一緒に中心となって考えるアンカーという役をやらせてもらいました。また2回目ということもあり、こどもたちと事前に何度も話し合い、より分かりやすく、面白く窯を焚くための新しいチャレンジをいくつか取り入れました。 2月、今年度2回目の登り窯を焚きました。今回私は、全体を見通し、こどもたちと一緒に中心となって考えるアンカーという役をやらせてもらいました。また2回目ということもあり、こどもたちと事前に何度も話し合い、より分かりやすく、面白く窯を焚くための新しいチャレンジをいくつか取り入れました。今回よかったことは、“よりこどもたちが考えて、理解して焚く”窯焚きができたことです。こどもたちの中からも、アンカーをやりたい子を募ってアンカーチームを作り事前の準備から段取りを取り進めていきました。登り窯は準備段階の作業がとても重要です。今までは大人が担っていた重要な準備の部分も今回はこどもたちと共に考えながら行いました。そこから、こどものアンカーと共に窯焚きの技術や自分たちが窯を焚くのだというプライドを得ることができました。また、それを自分たちの言葉で他のみんなに伝えていくことで、前回よりもさらにに窯焚きを考え、理解して焚くことができたと思います。私自身もこどもたち以上に窯への理解が進み、前回は参加者意識で行っていたものが、主体者意識へと変化しました。前回は窯が人の想いや意識で変化することが面白いと感じていたのですが、今回は面白さだけではなく、全体を見通す難しさ、決断していく責任の重さなども実感しました。意識や見方の変化で吸収できるものがこんなにも変わるのだということに驚くとともに、アンカーという経験をさせてもらえたことは本当にありがたかったと思っています。 3月、まとめに向けて  気が付いたらここでの生活も残り1か月をきり、終わりが見えてきました。私はここに来て、自分のことや、こどもたちのこと、暮らしのことなど、いろんなことを考え、悩み、学びました。その中で、たくさんの気持ちの変化がありました。こどもたちが自分たちの手で暮らしを掴んでいくことや、あきらめずに向き合い続ける大切さなど、私が実感したことを自分自身が持ち帰るとともに、ここに残し、引き継いでいってもらいたいと感じています。そのために今自分ができることは、私の想いや学びを書き残すこと、言葉で伝えること、行動で示すことなのではないかと思っています。 気が付いたらここでの生活も残り1か月をきり、終わりが見えてきました。私はここに来て、自分のことや、こどもたちのこと、暮らしのことなど、いろんなことを考え、悩み、学びました。その中で、たくさんの気持ちの変化がありました。こどもたちが自分たちの手で暮らしを掴んでいくことや、あきらめずに向き合い続ける大切さなど、私が実感したことを自分自身が持ち帰るとともに、ここに残し、引き継いでいってもらいたいと感じています。そのために今自分ができることは、私の想いや学びを書き残すこと、言葉で伝えること、行動で示すことなのではないかと思っています。まず、書くこと。私はここに来てたくさん文章を書くようになりました。通信を書いたり、日記を書いたり、手紙を書いたり、書くことで自分の想いが整理されたように思います。また、私の書いた文や絵をたくさんの人が読んでくれて、私に声をかけてくれました。みんなから反応がかえってくると、とても嬉しかったです。また、書くことが私にとって重要な情報発信手段なのだと思いました。今は私の学びノートを書いています。このノートをより多くの人に見てもらい、私がここで見たこと感じたことを知ってもらうことが、私の想いを残していくことにつながるのではないかと思っています。  次に、話すこと。私は自分が本当に思っていることを言葉で伝えることが苦手です。うまく伝わらなかったり、間違った伝わり方をしてしまう時もあります。面と向かって話すにはたくさんの勇気や気力、自信が必要だと思います。それでも残り数日でもっと自分が学び、自分の想いを伝えるためには、言葉にすることを恐れず、一人でも多くの人と話し、伝えあうことをしていきたいです。 次に、話すこと。私は自分が本当に思っていることを言葉で伝えることが苦手です。うまく伝わらなかったり、間違った伝わり方をしてしまう時もあります。面と向かって話すにはたくさんの勇気や気力、自信が必要だと思います。それでも残り数日でもっと自分が学び、自分の想いを伝えるためには、言葉にすることを恐れず、一人でも多くの人と話し、伝えあうことをしていきたいです。そして、行動すること。私がここで出会った人々には行動力があり、私もそんな人に憧れて、行動することを心がけて今まで過ごしてきました。行動で示すことには一番の説得力があります。また自分の想いを行動に移すことは難しいけれど、それを乗り越えた先には、行動した人にしか分からない面白さがあります。残り数日でやりたいことを一つずつ、着実に行動していきたいです。 これらのことを大切にしながら、焦らずゆっくりと残りの日々を過ごしていきたいです。 |
||
□ 研修担当あやおのふりかえり  ここでの暮らしなどを通して学んだことを、モノづくりや文章に起こしてまりお自身の中や、他の人にも見てもらえるよう、残そうとしている姿を最近よく見かけます。まりおはやりたいと思ったことについて人一倍努力する力があり、登り窯のアンカーや、3月の引き継ぎ会の総まとめなどの責任ある役割に対して、こどもたちと正面から向き合い、まりおが1年間育んできた力を思い存分発揮しています。 ここでの暮らしなどを通して学んだことを、モノづくりや文章に起こしてまりお自身の中や、他の人にも見てもらえるよう、残そうとしている姿を最近よく見かけます。まりおはやりたいと思ったことについて人一倍努力する力があり、登り窯のアンカーや、3月の引き継ぎ会の総まとめなどの責任ある役割に対して、こどもたちと正面から向き合い、まりおが1年間育んできた力を思い存分発揮しています。人当たりのいい性格のせいか、あまり本音を伝えるのが得意ではないと以前から言っていたまりおですが、よりだいだらぼっちを楽しくしようと、言葉にして伝える努力をしています。人に想いを伝えることはとても大変なことですが、ここでの暮らしを経て向き合う力がまりおの中で育ってきたのだと思います。あと1ヶ月と短い期間ですが、思い残すことのないよう頑張って欲しいです! |
||
| 1月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
「素」  新年が明け、今年の一字をみんなで発表しました。私は「素」という字を選びました。10か月間のここでの生活を通して感じているのは素朴なものを大切にできる人になりたいということです。 新年が明け、今年の一字をみんなで発表しました。私は「素」という字を選びました。10か月間のここでの生活を通して感じているのは素朴なものを大切にできる人になりたいということです。だいだらぼっちのこどもたちは「暮らし」を大切にして毎日を過ごしています。暮らしとは、三食ご飯を作って食べること、掃除、洗濯など家事をすることだけでなく、早寝早起き、体を動かし働いて、毎日健康に暮らすこと、身の周りに在る人や自然、四季と共に生きることなど素朴なことだと思っています。毎日体を動かすここでの生活では、大好きなおしゃれはなかなかできないし、コンビニや地下鉄など手軽で便利なものもありません。それでもここの暮らしには、都会で慌ただしく過ごしていたらきっと気付けない、素朴な豊かさがあります。 草木や動物たちが人間の生活に不可欠な存在であること、二十四節気や季節に沿った昔の人々の暮らしがとても賢く考えられていて、理に適ったものであることなどここでの暮らしを通して気付いたことはたくさんありました。また人との出会いやゆっくりとした暮らしの中で自分を見つめる余裕も生まれ、自分に素直になる気持ちや人に今まで以上に感謝する気持ちも生まれました。 今は不器用でどれだけ時間がかかっても、自分の手で暮らしを作り、自分の足で歩くここでの暮らしそのものが、私自身を豊かにしてくれていると感じています。残されたここでの2か月間はもちろん、この先も、そんな素朴な暮らしと謙虚に向き合いながら、より豊かな人間に成長していきたいです。 やってみないと何も分からない  私はここに来て木工、陶芸、草木染めなど、常にものづくりをしています。今月は野焼き、木のスプーン、皿づくり、クサギ染めなどを行いました。ものづくりは私の趣味でもあるのですが、作れば作るほどに学びや発見があります。先日行った野焼きではみんなで埴輪や土器を作り、チームに分かれて焼きました。実際に焼く前はちゃんと焼けるのか不安でチームで何度も話し合いました。私達のチームは石や藁を駆使して挑戦しました。焼き物が炎に包まれ、白く輝く状態を目にしたときはとても感動しました。最後にはきれいな茜色に焼けた土器や真っ黒になった埴輪、爆発して粉々になった器など様々な作品が出来上がり、焚きあがった嬉しさと誇らしさをお互いに自慢し合いました。いろんな仕上がりになることを知識として知ってはいても、実際にやってみることで、ものの見え方は全く変わってきます。今まではただ大雑把で単純に作られていると思っていた縄文土器が実は賢い縄文人たちによって熟考されて繊細に作られていたのだということが分かったり、普段なかなか考えない、「焚火って何度くらいあるんだろう?」「どうして土が石になるんだろう?」といったことを考えたりするきっかけになりました。 私はここに来て木工、陶芸、草木染めなど、常にものづくりをしています。今月は野焼き、木のスプーン、皿づくり、クサギ染めなどを行いました。ものづくりは私の趣味でもあるのですが、作れば作るほどに学びや発見があります。先日行った野焼きではみんなで埴輪や土器を作り、チームに分かれて焼きました。実際に焼く前はちゃんと焼けるのか不安でチームで何度も話し合いました。私達のチームは石や藁を駆使して挑戦しました。焼き物が炎に包まれ、白く輝く状態を目にしたときはとても感動しました。最後にはきれいな茜色に焼けた土器や真っ黒になった埴輪、爆発して粉々になった器など様々な作品が出来上がり、焚きあがった嬉しさと誇らしさをお互いに自慢し合いました。いろんな仕上がりになることを知識として知ってはいても、実際にやってみることで、ものの見え方は全く変わってきます。今まではただ大雑把で単純に作られていると思っていた縄文土器が実は賢い縄文人たちによって熟考されて繊細に作られていたのだということが分かったり、普段なかなか考えない、「焚火って何度くらいあるんだろう?」「どうして土が石になるんだろう?」といったことを考えたりするきっかけになりました。 「百聞は一見にしかず、百見は一行にしかず」という言葉を教えてもらいました。私は日々この言葉の意味を実感しています。木のスプーンを作ることは本当に難しいことなのか、薪で毎日風呂を焚くことや車で15分の道のりを1時間歩くことが本当に大変なことなのか、全部やってみないと分かりません。やってみて楽しかったり感動したり疲れたりした経験そのものが私にとっての学びなのだということを実感しています。 「百聞は一見にしかず、百見は一行にしかず」という言葉を教えてもらいました。私は日々この言葉の意味を実感しています。木のスプーンを作ることは本当に難しいことなのか、薪で毎日風呂を焚くことや車で15分の道のりを1時間歩くことが本当に大変なことなのか、全部やってみないと分かりません。やってみて楽しかったり感動したり疲れたりした経験そのものが私にとっての学びなのだということを実感しています。 |
||
□ 研修担当いとのふりかえり  3学期に入り終わりの見えてきたここでの生活。まりおはやりきるために、やることをすべて書き出し、計画を立て、一つずつ確実に達成しています。 3学期に入り終わりの見えてきたここでの生活。まりおはやりきるために、やることをすべて書き出し、計画を立て、一つずつ確実に達成しています。まりおとふりかえりをして感じたことは、まりおがこの数か月、泰阜の自然、移りかわる四季、村の人、こどもとの暮らしから学んだことが、ひとつになりつつあるということです。それは今回ふりかえった中で出てきた、「素朴な暮らしを大切にできる人になりたい」という想いに繋がっています。 当初、まりおは「こどもとの信頼関係作り」に頭を悩ませていたそうです。ただ今は、自分が感じた豊かさを今度は別の人に伝えていく。その先に信頼関係が生まれるのではないかと話していました。これは、「信頼」という一言で終わっていたことが、この一年間の暮らしを通して、ひとつひとつ形になっていったからこそ生まれた考えだと思います。このことは信頼だけではなく、「楽しかったこと」「大変だったこと」「大切だと思ったこと」「感動したこと」など、全てに言えることでしょう。その積み重ねこそが、まりおの言う「豊かさ」のように感じました。 残りわずかとなった、ここでの生活。最後まで自分の「素」を大切に、全力でやりきってほしいと思います。 |
||
| 12月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
登り窯 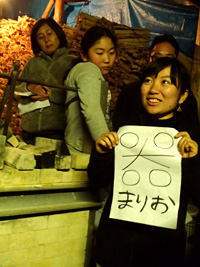 12月半ば、登り窯を行いました。登り窯では、2学期に自分たちが製作した陶芸作品を自分たちで焼きます。4日間当番交代制で薪をくべ、窯の温度を1200℃まで上げて焚きつづけるビックイベントです。始める前にレクチャーを受けたものの、あまり想像がつかず、どうやったら温度が上がるか、火や窯の中の様子、温度の変動のリズムなど、やりながら感覚をつかんでいきました。 12月半ば、登り窯を行いました。登り窯では、2学期に自分たちが製作した陶芸作品を自分たちで焼きます。4日間当番交代制で薪をくべ、窯の温度を1200℃まで上げて焚きつづけるビックイベントです。始める前にレクチャーを受けたものの、あまり想像がつかず、どうやったら温度が上がるか、火や窯の中の様子、温度の変動のリズムなど、やりながら感覚をつかんでいきました。その中でも、興奮、焦り、緊張など、窯場のメンバーの気持ちが混じりあうことで作られる独特の雰囲気に私自身もとても高揚しました。当番が交代するタイミングになると、それまで順調に温度が上がっていたとしても、急に上がらなくなることがあります。こどもたちは、「人が変わったことを窯に気づかれちゃった!」と表現していました。私はその時、人の集中力や窯に対する熱意の差、感覚の違いや個性などすべてが窯に伝わっているのだということを感じました。続けて窯を見ていた人と新しく入ってきた人との温度差は大きいと思います。私は4回当番に入り、空気感の違いに戸惑うこともありました。しかし、徐々にお互いの気持ちや熱意を合わせること、毎回違うメンバーでコミュニケーションをとり、そのメンバーでしかできない窯焚きを作っていくことは難しいのですが面白く、一つの社会のように思えました。窯焚きのノウハウを得ることだけではなく、そういった場面に出会えることに、こどもたちがここで窯焚きを行う意味があるのだということを感じました。 窯は生き物です。焼き物を焼くということは化学ですが、それだけではない、みんなの想いがその出来を左右すると実感しました。この登り窯で焚き上げた作品は素晴らしいものばかりで、すべて私の宝物になりました。 お年とりキャンプ  年末年始は山賊キャンプのお年とりコースに参加しました。 年末年始は山賊キャンプのお年とりコースに参加しました。キャンプ中の夜ごはんにみんなで天ぷらを作りました。その天ぷらに合わせて、  中学生の女の子が天つゆを作ってくれました。小学生の女の子がその天つゆに大喜びで、作ってくれた女の子に、「この天つゆ、本当に美味しい!」と言うと、嬉しさのあまり中学生の女の子は泣いてしまいました。小学生の女の子は他にもいろんな遊びをした中でこのことがキャンプで一番心に残ったと話していました。 中学生の女の子が天つゆを作ってくれました。小学生の女の子がその天つゆに大喜びで、作ってくれた女の子に、「この天つゆ、本当に美味しい!」と言うと、嬉しさのあまり中学生の女の子は泣いてしまいました。小学生の女の子は他にもいろんな遊びをした中でこのことがキャンプで一番心に残ったと話していました。私はこの二人の女の子の素直さに感動しました。こどもたちはどんな小さな出来事や瞬間にも、言葉のひとつひとつをよく考え、感じているのだということに気が付きました。そして、心からの素直な言葉は人の心を動かすのだということを改めて感じました。 キャンプでもだいだらぼっちの暮らしの中でもこどもたちに教えられること、気付かされることはたくさんあります。そんなときに考えるようになったのは、子どもも大人も同じ「人」であり、ちゃんといろんなことを考えて、意思を持って生きているということです。当たり前のことのようですが、つい忘れがちになってしまうことでもあります。でも常に「大人」対「子ども」ではなく、「人」対「人」で謙虚に接することで、学ぶこと、気付くことが増えるのではないかと思っています。 残り3か月  12月に入り、残りの期間を徐々に意識するようになってきました。12月は上に挙げたような大きなイベントがあり、そこから学ぶことも多かったのですが、そんな中でも毎日の暮らしをいい加減にしないことを意識しました。私がここで暮らせる期間は残り3か月、1日1日が勝負です。とにかく1日でも無駄にしないように、やりたいことをやりきろうと思っています。毎日犬の散歩に行くことや早朝にものづくりをすること、夜に日記を書くことなど、ここに来て日課になったことも増えてきました。一見どうでもいいことのようですが、そこには自然や暮らし、自分を見つめるためのいろんな発見があり、私にとっては学びが詰まった大切な時間です。来月はもっと草花や鳥を観察し、焼き物や火のことを勉強したいと思っています。これらを勉強することで、泰阜という地をもっと知り、この地に根差したより面白い暮らしをしたいと思ったからです。私がここで行動することで出会うもの、生まれるものがきっとこどもたちの学びにもつながることと信じて、ここでの残り3か月を一生懸命生きたいと思います 12月に入り、残りの期間を徐々に意識するようになってきました。12月は上に挙げたような大きなイベントがあり、そこから学ぶことも多かったのですが、そんな中でも毎日の暮らしをいい加減にしないことを意識しました。私がここで暮らせる期間は残り3か月、1日1日が勝負です。とにかく1日でも無駄にしないように、やりたいことをやりきろうと思っています。毎日犬の散歩に行くことや早朝にものづくりをすること、夜に日記を書くことなど、ここに来て日課になったことも増えてきました。一見どうでもいいことのようですが、そこには自然や暮らし、自分を見つめるためのいろんな発見があり、私にとっては学びが詰まった大切な時間です。来月はもっと草花や鳥を観察し、焼き物や火のことを勉強したいと思っています。これらを勉強することで、泰阜という地をもっと知り、この地に根差したより面白い暮らしをしたいと思ったからです。私がここで行動することで出会うもの、生まれるものがきっとこどもたちの学びにもつながることと信じて、ここでの残り3か月を一生懸命生きたいと思います |
||
□ 研修担当いっちーのふりかえり  登り窯にお年とりキャンプとビッグイベントのあった12月。その中でも、マリオは「毎日の暮らしをいい加減にしない」ことを意識して過ごしました。こどもたちと一緒におこなった登り窯は、毎日の掃除・洗濯・ごはん作りなどの暮らしをしたうえでやりきるからこそのビッグチャレンジです。暮らしという土台があり、そこがしっかりしているからこそ、自分も含めみんな安心して挑戦することができるということを改めて、実感したようです。また、マリオには木工やツル細工、村を巡ること、植物を知ること、ごはん作りなどやりたいことが何十個もあります。だからこそ、残り3ヶ月という時間の中でやりきるため、1日1日を無駄にしたくないという思いもあるようです。 登り窯にお年とりキャンプとビッグイベントのあった12月。その中でも、マリオは「毎日の暮らしをいい加減にしない」ことを意識して過ごしました。こどもたちと一緒におこなった登り窯は、毎日の掃除・洗濯・ごはん作りなどの暮らしをしたうえでやりきるからこそのビッグチャレンジです。暮らしという土台があり、そこがしっかりしているからこそ、自分も含めみんな安心して挑戦することができるということを改めて、実感したようです。また、マリオには木工やツル細工、村を巡ること、植物を知ること、ごはん作りなどやりたいことが何十個もあります。だからこそ、残り3ヶ月という時間の中でやりきるため、1日1日を無駄にしたくないという思いもあるようです。毎日の暮らしも、やりたいことも全部やりきるというのは簡単なことではありません。マリオは「やっていくうえで学んだことでこどもたちの可能性が広がったらうれしい」と言っていました。熱意を絶やさず、考え、悩み、やりきった人にしかわからないことは、たくさんあります。その積み重ねが人としての深みであり、先生になった時どれだけのことを伝えられるかということでもあると思います。様々な個性を持ったこどもと接する中で、どれが興味を引き、何が関係性を作っていくきっかけになるか分かりません。だからこそ、残りの時間を大切にやりたいことをやりきって欲しいと思います。 |
||
| 11月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
村を歩いて得たもの  先月の研修で刺激を受け、11月は週に1回村を巡って学ぶことを大きなテーマとして1カ月を過ごしました。近所のおばあちゃんの家に行ったり、片道1時間歩いて隣の集落に遊びに行ったり、まだ歩いたことのない道を歩いてみたりと、とにかく外に出る事を意識して過ごしました。村の人のお宅では、昔、こんにゃくで生計を立てていた暮らしのことや、今に繋がる蜂つけなどの暮らしの知恵のお話を聞きました。いろんな場所で聞いたお話が繋がり、新しいことが分かったり、自分が今まで見ていた泰阜村の景色と繋がり、今まで気付かなかった景色に気付いたり、いろんな視点や価値観を得ること、人や物のつながりを見ることができました。 先月の研修で刺激を受け、11月は週に1回村を巡って学ぶことを大きなテーマとして1カ月を過ごしました。近所のおばあちゃんの家に行ったり、片道1時間歩いて隣の集落に遊びに行ったり、まだ歩いたことのない道を歩いてみたりと、とにかく外に出る事を意識して過ごしました。村の人のお宅では、昔、こんにゃくで生計を立てていた暮らしのことや、今に繋がる蜂つけなどの暮らしの知恵のお話を聞きました。いろんな場所で聞いたお話が繋がり、新しいことが分かったり、自分が今まで見ていた泰阜村の景色と繋がり、今まで気付かなかった景色に気付いたり、いろんな視点や価値観を得ること、人や物のつながりを見ることができました。また移動にはなるべく自分の足を使いました。行くことのできる距離は限られるけれど、歩かないと分からない発見がたくさんありました。毎日歩く道で昨日まで緑色だった実が黒くなっていたときに嬉しくなったり、すれ違う人とお話したり、サルや鳥の鳴き声に立ち止まって姿を探してみたりして、遊び道具を手に入れなくても、面白いものは身近にたくさんあるのだということを実感しました。すると興味の幅が広がっていって、毎日新しい草木を覚え、季節の変化に敏感になり、こどもたちと共有できることやチャレンジできることが増えていくのだと感じました。 「まりおの授業」をやってみて 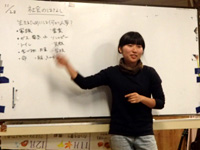 「まりおが来年から先生になるから、来年困らないように授業の練習ができる機会をつくろう!」とこどもたちが提案をしてくれて、私がこどもたちに向けて授業をする時間を作ってくれました。先月の研修で感動したこんにゃく作りとそこから泰阜村の産業、社会とのつながりを考えられる授業をしようと考え、産業の話とこんにゃく作りの授業を行いました。 「まりおが来年から先生になるから、来年困らないように授業の練習ができる機会をつくろう!」とこどもたちが提案をしてくれて、私がこどもたちに向けて授業をする時間を作ってくれました。先月の研修で感動したこんにゃく作りとそこから泰阜村の産業、社会とのつながりを考えられる授業をしようと考え、産業の話とこんにゃく作りの授業を行いました。授業当日、こんにゃく作りの中で火傷をしてしまった子がいました。原因はこどもたちに危険喚起がしっかりできていなかったこと、準備の段階で授業の構成やどうしたら子どもたちが興味を持てる授業ができるのかとばかり考えていて、基本的な安全管理の視点が欠けていたことが一番の要因でした。 授業の内容自体も、伝えたいことが明確でなかったこと、こんにゃく作りから産業の話、社会の話につなげることが強引だったことなど、反省点が多くなってしまいました。 後に授業を振り返ったときには、来年教壇に立つ自信を失うくらいに反省点が多く、落ち込んでいたのですが、こどもたちが、私が伝えようとしたことを一生懸命考えてくれたり、ノートにまとめて見せてくれたり、感想を言いに来てくれたりしました。そんな子どもたちに勇気づけられ、「またやりたい!」と声をかけてもらい、来月も授業をやらせてもらえることになりました。授業をやろうと提案してくれたところから全部、気付いたらこどもたちに助けられ、支えられていました。そんなこどもたちに誠実に向き合うためにも、今回の失敗をただの失敗で終わらせず、次につなげられる学びに変えていきたいと思います。 基本に立ち返る  村を巡ること、授業をしたことなどの11月の活動から感じたことは「基本に立ち返る」ということです。2学期も佳境に入り、ここでの暮らしがどんどん楽しくなっていく中で、もう一度、安全管理や体調管理、あいさつをすること、衣食住のことなどの暮らしの基本的な部分を見直し、引き締めなければならないと感じています。 村を巡ること、授業をしたことなどの11月の活動から感じたことは「基本に立ち返る」ということです。2学期も佳境に入り、ここでの暮らしがどんどん楽しくなっていく中で、もう一度、安全管理や体調管理、あいさつをすること、衣食住のことなどの暮らしの基本的な部分を見直し、引き締めなければならないと感じています。安定したフィールドがある上でこそ、自分も子どもたちも豊かな暮らしや学びを得られるのであって、その部分を甘く見ると様々なバランスが崩れてしまうのだということを感じています。 12月は登り窯や冬キャンプなど、非日常の行事がたくさんあります。わくわくする思いがとても大きいですが、それと同時に常に基本に立ち返り、危険なことはないか、誰かひとりが苦しんでいないかなど、気をきかせることのできる人間になりたいと思います。 |
||
□ 研修担当のりのふりかえり 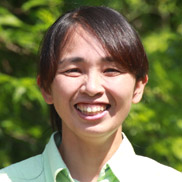 11月は「村を巡ること」をテーマとして過ごしたマリオ。しっかりとそのテーマ通り、1週間に1度のペースで村のおじいさん、おばあさんのお宅を巡り、様々な人に出会っていく中で、さらに多くの価値観を得ることができたようです。 11月は「村を巡ること」をテーマとして過ごしたマリオ。しっかりとそのテーマ通り、1週間に1度のペースで村のおじいさん、おばあさんのお宅を巡り、様々な人に出会っていく中で、さらに多くの価値観を得ることができたようです。そして、月の後半では、ここ数か月間でインプットしてきた様々な経験や価値観をこどもたちに「授業」としてアウトプットする機会を得ましたが、アウトプットするにあたってはまだまだ基本的な計画性に欠ける部分もあり、けが人を出してしまい、とても落ち込んでしまったマリオでした。 人に伝えるにあたっては、得たものを整理し、自分の中に落とし込み、本当に伝えたいこと、伝えるべきことを整理する。そして、なにより子どもたちの様子や反応、安全面にに注意を払う。そんな「基本」の部分が大切になってきます。4月からのだいだらぼっちの暮らしを通して日常としてはわかっていた「基本」の部分も「授業」という形になったら、途端に難しいことも出てきます。今後、マリオが働く学校現場では1人で40人ほどのこどもたちに伝えることとなります。より多くの子どもたちに伝えるためにはさらに「基本」の部分が大切になってくることでしょう。 今回の「授業」では失敗を経験したマリオですが、こどもたちからもらったチャンスを生かし、来月は「基本」の部分も大切にしながら再チャレンジしてほしいと思います。 残り数か月、より多くの価値観を子どもたちに伝えられる教育者になれるようがんばってください。 |
||
| 10月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
研修で出会えたもの  今月はものづくりの先生ぎっく、まるちゃんが主催する保育士の研修に参加して、4日間、「梨久保」というだいだらぼっちがある場所よりさらに山奥の集落でキャンプをしました。4人の保育士さんたちとやりたいことを出し合い、自分たちでスケジュールを組み、村で採れた栗で栗ごはんを作ったり、きな粉を挽いておはぎを作ったり、一人野宿をしたり、インディアンの住居のティピーを建て、その中で火を焚いたりと参加者が主体的に活動するフリーキャンプを行いました。 今月はものづくりの先生ぎっく、まるちゃんが主催する保育士の研修に参加して、4日間、「梨久保」というだいだらぼっちがある場所よりさらに山奥の集落でキャンプをしました。4人の保育士さんたちとやりたいことを出し合い、自分たちでスケジュールを組み、村で採れた栗で栗ごはんを作ったり、きな粉を挽いておはぎを作ったり、一人野宿をしたり、インディアンの住居のティピーを建て、その中で火を焚いたりと参加者が主体的に活動するフリーキャンプを行いました。盛りだくさんなスケジュールの中でも今回のキャンプの目玉は、梨久保のおじいちゃん、おばあちゃんに藁草履づくりを教えてもらう交流会でした。会では、20年ぶりだと言って思い出しながら、魔法のように藁をなっていくおじいちゃんたちの手さばきに感動したり、藁草履をはいて2時間かけて学校へ行くのが当たり前だった話を聞いて驚いたりしました。他にも、田んぼができない代わりにこんにゃくで生計を立てていたこと、戦後の厳しいときは葉っぱや木の実を米に混ぜていたことなど、おじいちゃんたちが話してくれた暮らしのことは、梨久保の風土や季節に合わせた必然と言えるようなことばかりでした。そこには厳しい山奥で生き抜くための技術や知恵がたくさん詰まっていました。今がどんなに便利な時代であっても、おじいちゃんたちが築いてきたものがあるからこそ、今があるのであって、そこにある暮らしの知恵や思いを私達は忘れてはならないのだということを感じました。  梨久保は全部で6軒しかなく、そのほとんどが80歳以上の高齢者が住むという限界集落です。5年後、10年後にはどうなっているか分からないような場所ですが、80年以上もの間、厳しい山奥で生き抜いてきた知恵や技をたくさんもっていて、1日1日を力強く生きる人たちが住む、宝物のような場所だということを知りました。この研修での貴重な出会いを感謝の気持ちに代えて、今回の学びをダイダラボッチのこどもたちに伝えていかなければならないと思っています。 梨久保は全部で6軒しかなく、そのほとんどが80歳以上の高齢者が住むという限界集落です。5年後、10年後にはどうなっているか分からないような場所ですが、80年以上もの間、厳しい山奥で生き抜いてきた知恵や技をたくさんもっていて、1日1日を力強く生きる人たちが住む、宝物のような場所だということを知りました。この研修での貴重な出会いを感謝の気持ちに代えて、今回の学びをダイダラボッチのこどもたちに伝えていかなければならないと思っています。これからやりたいこと 今回の研修で私が残り5か月、ここで何をしたいかということが明確になってきました。私は私にしかできないことをしたいと思います。ダイダラボッチの大人の中でも、よりフリーに動ける立場だからこそ、もっと村に出て学ぶこと、そこで得た縁を大切にして自分から積極的に繋がること、いろんなものを作ることを行っていきたいです。そこで面白かったこと、感動したこと、こどもたちと一緒にやりたいと思ったことをこどもたちと共有して、一緒に面白いと思ったり、感動したりすることが私にできることだと思っています。  私は4月当初、「こどもたちとの信頼関係を結ぶためにどうすればいいのかを学びたい」と言ってここに来ました。しかし今は少し自分の中でのテーマが変わってきているように感じます。せっかく泰阜村にあるだいだらぼっちに来たのだから、もっと村の良さを見つけて自分のホームにすること、もっと自分が楽しんで、いっぱい経験することで自分の発言に説得力や面白さを持たせること、こどもたちに「まりおって面白いな!」って思ってもらえるような人間になることが今の目標です。そしてその結果としてこどもたちとの信頼が生まれるのなら、それに越したことはありません。 私は4月当初、「こどもたちとの信頼関係を結ぶためにどうすればいいのかを学びたい」と言ってここに来ました。しかし今は少し自分の中でのテーマが変わってきているように感じます。せっかく泰阜村にあるだいだらぼっちに来たのだから、もっと村の良さを見つけて自分のホームにすること、もっと自分が楽しんで、いっぱい経験することで自分の発言に説得力や面白さを持たせること、こどもたちに「まりおって面白いな!」って思ってもらえるような人間になることが今の目標です。そしてその結果としてこどもたちとの信頼が生まれるのなら、それに越したことはありません。残り5か月しかないだいだらぼっちでの生活ですが、今はやりたいことで溢れていて残りの5か月が楽しみで仕方がありません。この気持ちを持ち続け、残り5か月を駆け抜けたいと思います。 |
||
□ 研修担当バズのふりかえり  10月の研修では保育士の研修に参加ということで、ダイダラボッチと対象は違いますが、同じ教育というフィールドで活動している人たちとの出会いは、マリオにとって圧倒的に収穫のあった月になったようです。見ず知らずの場所に飛び込み、初めてのことにチャレンジすることや他人との向き合い方など保育士さん達の真摯な姿勢に感動していました。また、一歩引いて見ることで、自身の生活を振り返ったり、「こうすればいいのにな」という自分では見つからなかった新たな気づきになり、マリオが泰阜村で積み上げてきた7ヵ月の経験を確かな学びにつなげていました。ダイダラボッチではこどもも大人も自分のやりたいことにチャレンジできます。しかし、やりたいという気持ちを行動につなげなければあっという間に1年が過ぎて行ってしまします。ダイダラボッチの中だけにこだわらず、泰阜村という大きなフィールドをつかって活動することで、新たな出会いや学びにつながるはずです。視野を広く持ち、様々な出会いを残りの数か月にぶつけて欲しいです。 10月の研修では保育士の研修に参加ということで、ダイダラボッチと対象は違いますが、同じ教育というフィールドで活動している人たちとの出会いは、マリオにとって圧倒的に収穫のあった月になったようです。見ず知らずの場所に飛び込み、初めてのことにチャレンジすることや他人との向き合い方など保育士さん達の真摯な姿勢に感動していました。また、一歩引いて見ることで、自身の生活を振り返ったり、「こうすればいいのにな」という自分では見つからなかった新たな気づきになり、マリオが泰阜村で積み上げてきた7ヵ月の経験を確かな学びにつなげていました。ダイダラボッチではこどもも大人も自分のやりたいことにチャレンジできます。しかし、やりたいという気持ちを行動につなげなければあっという間に1年が過ぎて行ってしまします。ダイダラボッチの中だけにこだわらず、泰阜村という大きなフィールドをつかって活動することで、新たな出会いや学びにつながるはずです。視野を広く持ち、様々な出会いを残りの数か月にぶつけて欲しいです。頑張れ、まりお! |
||
| 9月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
もっと深く学ぶ  最近は、こどもたちとの暮らしだけでなく、山村の暮らしから学ぶことの面白さを感じるようになりました。草刈りや畑作業、薪で火を焚くことなど、都会ではあまり馴染みのなくなってしまったことを泰阜村の人々は今も当たり前に行っています。今月は村の人々と関わる機会が何度かあり、そこに暮らしの知恵や自然と共生していくための工夫がたくさん詰まっているということに改めて気がつきました。また、だいだらぼっちでもこういったことは日常で行われているのだけれど、ここに来た当初は風呂焚きひとつに感動していたことが、私の中でも徐々に当たり前になってきて、そこから学ぶという意識が薄れてきていたのではないかということにも気が付きました。学びの種は身近にたくさん転がっていて、それを実にするかどうかは自分次第なのだということを強く実感しました。 もっと村に出て、自然や人に触れて、だいだらぼっちという場を改めてこどもたちと一緒に見直すことで、この私自身の学びをこどもたちと共有し、還元したいと思っています。 バランスを考える  9月に入ると、秋の気配がどんどん色濃くなってきて、収穫した栗で栗きんとんや栗ごはんを作ったり、お月見をしたり、村めぐりや散歩に出掛けて遊んだりと、9月にしかできない遊びや今だからこそ楽しいことをいっぱいしようと思い、盛りだくさんの毎日でした。そして、やりたいことだけではなく、畑に何を植えるのかの話し合い、田んぼの草取りや、薪の蓄え、草刈りなどやらなければいけないことも絶えず、大忙しでした。やりたいことをやるだけじゃ暮らすこと、生きることは成り立たない、しかし季節は待ってくれない。このバランスを保つことは難しいけれど、この先もきっと常に直面していく課題なのだろうということを感じました。このことを負担にとらえるのではなく、だいだらぼっちの一員として、また村民の一員として、人とのつながりの下、賢く手間をかけた暮らしをつくるための段取りを取ること、そしてバランスを保つことを楽しむことができたら、ここで暮らすことの意味が深まり、もっと面白くなるのではないかと感じています。 9月に入ると、秋の気配がどんどん色濃くなってきて、収穫した栗で栗きんとんや栗ごはんを作ったり、お月見をしたり、村めぐりや散歩に出掛けて遊んだりと、9月にしかできない遊びや今だからこそ楽しいことをいっぱいしようと思い、盛りだくさんの毎日でした。そして、やりたいことだけではなく、畑に何を植えるのかの話し合い、田んぼの草取りや、薪の蓄え、草刈りなどやらなければいけないことも絶えず、大忙しでした。やりたいことをやるだけじゃ暮らすこと、生きることは成り立たない、しかし季節は待ってくれない。このバランスを保つことは難しいけれど、この先もきっと常に直面していく課題なのだろうということを感じました。このことを負担にとらえるのではなく、だいだらぼっちの一員として、また村民の一員として、人とのつながりの下、賢く手間をかけた暮らしをつくるための段取りを取ること、そしてバランスを保つことを楽しむことができたら、ここで暮らすことの意味が深まり、もっと面白くなるのではないかと感じています。まだまだ足りない勇気 7,8月の振り返りで『伝える』ということについて課題をあげましたが、このことに関しては、まだなかなか向き合うことができていません。例えば、畑の話し合いの時に、「もっとテーマを決めて畑をやったりしたら面白くなりそうだけどなあ。」などと心の中で思っても、否定されたり、話が複雑になるのを面倒くさがり伝えることをしないことがありました。伝えるという訓練をしないと上達しないということは分かってはいるのだけれど、相手に何を思われるか、こんな浅い知識のま  まで偉そうに語って良いのか、などいろんなことを考えて躊躇してしまう自分がいました。9月の振り返りでなおみちから、「浅いか深いかじゃなくて、自分がどれだけの思いで学んでいて、そこで得たまりおの感動をいかにつたえられるかどうかだよ」という言葉をかけてもらいました。そして、まだまだ私が自分と人とを比べ、自分自身と本当に向き合えていないのだということに気付きました。もっと素直に、簡単に、主観的に、自分の思いを伝えること、そしてそれを自信に変えていくことを行っていきたいです。ここを乗り越えることができたら、きっともっとこどもたちとの関係も深まっていくのではないかと思っています。 まで偉そうに語って良いのか、などいろんなことを考えて躊躇してしまう自分がいました。9月の振り返りでなおみちから、「浅いか深いかじゃなくて、自分がどれだけの思いで学んでいて、そこで得たまりおの感動をいかにつたえられるかどうかだよ」という言葉をかけてもらいました。そして、まだまだ私が自分と人とを比べ、自分自身と本当に向き合えていないのだということに気付きました。もっと素直に、簡単に、主観的に、自分の思いを伝えること、そしてそれを自信に変えていくことを行っていきたいです。ここを乗り越えることができたら、きっともっとこどもたちとの関係も深まっていくのではないかと思っています。 |
||
□ 研修担当なおみちのふりかえり  「ものごとの本質を考えること」と「主体的に考える(受け身にならない)」ということを念頭にすごした9月。まりおは、村をたくさん歩き新しい出会いもして、これまでの体験の点と点が線でつながったことで“暮らしから学ぶ”“生きる”ということが、スッと沁みてきたようです。 「ものごとの本質を考えること」と「主体的に考える(受け身にならない)」ということを念頭にすごした9月。まりおは、村をたくさん歩き新しい出会いもして、これまでの体験の点と点が線でつながったことで“暮らしから学ぶ”“生きる”ということが、スッと沁みてきたようです。これまで、一生懸命で優しい性格ゆえに悩み、足踏みしてきたこともあったかと思いますが、季節に追われながら忙しい毎日をひた走り、気が付いたら自分の枠を超えていたまりおの学びは「考えるって楽しい!学ぶって嬉しい!」という素直な喜びが伝わってくるものでした。 学びも信頼関係も「深める」面白さや心地よさは、未知に踏み込むことなのかもしれません。今のまりおなら、安全圏から一歩踏み出す勇気とともに、ごまかさないで自分の本質と向き合う懐も育てていけるでしょう。その主観的な積み重ねが客観的な視点を育て、広くて深い心を育てるのだと思います。それはきっと一生懸命、格好悪く生きること。でも、その方が人生は面白く、こどもたちの心に触れる力にもなるはずです。 泣きながらでも諦めない挑戦者、まりお。キラキラ愛に満ちた先生になってくれると確信しています。 |
||
| 7月・8月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
仲間がいる心強さ  キャンプ期間中、裏方にいる時は大人だけで過ごす時間が多く、スタッフや裏方ボランティアさん達と、キャンプの様子やだいだらぼっちの1学期の出来事など、いろいろな話をしました。また、普段だいだらぼっちで一緒に過ごしているスタッフと一緒にキャンプの現場にも出て、子どもたちが誇りを持てるキャンプにしよう、子どもたちや相談員と共に夢を語れるキャンプを作ろうと、たくさんの話をし、たくさんの連携を行いました。5か月間共に暮らし、思いを語り合っている仲間だからこそ、私はとても信頼し、安心してキャンプに取り組むことができました。また、私がキャンプ中に体調を崩してしまったときも、「ここまでよく支えてくれてありがとう。」「しっかり休んで早く戻ってこい。」と声をかけてもらい、みんなが心配してくれて、支えてくれて、仲間がいることの心強さを改めて実感しました。 キャンプ期間中、裏方にいる時は大人だけで過ごす時間が多く、スタッフや裏方ボランティアさん達と、キャンプの様子やだいだらぼっちの1学期の出来事など、いろいろな話をしました。また、普段だいだらぼっちで一緒に過ごしているスタッフと一緒にキャンプの現場にも出て、子どもたちが誇りを持てるキャンプにしよう、子どもたちや相談員と共に夢を語れるキャンプを作ろうと、たくさんの話をし、たくさんの連携を行いました。5か月間共に暮らし、思いを語り合っている仲間だからこそ、私はとても信頼し、安心してキャンプに取り組むことができました。また、私がキャンプ中に体調を崩してしまったときも、「ここまでよく支えてくれてありがとう。」「しっかり休んで早く戻ってこい。」と声をかけてもらい、みんなが心配してくれて、支えてくれて、仲間がいることの心強さを改めて実感しました。そういった大人同士の関わりの時間が多かったことで、子どもだけでなく、スタッフと思いを語り合ったり、感じたことを共有したりすることの大切さを実感しました。私は、子どもたちとの信頼関係について学びたいと思い、ここに来ましたが、子どもたちとの信頼関係だけでなく、大人同士の信頼関係やチームワークが子どもたちや自分自身を成長させるためにはとても重要なのだということを感じました。 私の原動力  3か月半だいだらぼっちでこどもたちと過ごし、こどもたちとの関わりの中で大切にしたいことが定まってきていたこともあり、去年以前にボランティアで山賊キャンプに参加していたときよりも、迷いが少なく、見通しをもってキャンプを行うことができました。私は目標を「参加者全員が安心して思いっきり楽しむことのできる場づくりをすること」と定め、本部スタッフとして7泊8日のキャンプに参加しました。食材や調理器具の整理や炊き出し、こどもたちがやりきれなかった部分の掃除、料理や木工で怪我をしないための安全管理など、とにかく土台を支えることに取り組みました。 3か月半だいだらぼっちでこどもたちと過ごし、こどもたちとの関わりの中で大切にしたいことが定まってきていたこともあり、去年以前にボランティアで山賊キャンプに参加していたときよりも、迷いが少なく、見通しをもってキャンプを行うことができました。私は目標を「参加者全員が安心して思いっきり楽しむことのできる場づくりをすること」と定め、本部スタッフとして7泊8日のキャンプに参加しました。食材や調理器具の整理や炊き出し、こどもたちがやりきれなかった部分の掃除、料理や木工で怪我をしないための安全管理など、とにかく土台を支えることに取り組みました。そういった作業は単調になりがちですが、私はとても楽しく行うことができました。同じ作業を自分のためだけに一人でやってもきっとそこにやりがいや楽しさは見出せないと思います。私が本部スタッフとして行うすべての作業には、「こどもたちや相談員、みんなのために」という目的がありました。その目的があり、ふとしたときに「まりおの作るごはん、本当においしいんだよね。」と声をかけてもらえることが、私の原動力になっていました。そして、私は仲間のために本気になることや、本気で向き合える仲間に憧れてここに来たのだということを改めて感じ、仲間や相手を大切に思う気持ちをこの先も持ち続けなければいけないのだということを感じました。 キャンプを通して見えた課題  キャンプの中では、裏で作業をするばかりではなく、道具の使い方の説明や、長老(現場責任者)がいないときなど、みんなの前で話をするチャンスもたくさんありました。しかし、いざ実際に前に立って話してみると、話が長くなってしまったり、淡々として面白さがなかったり、こどもたちを引き付けられず、なかなか思うようにいきませんでした。キャンプ前にリスクマネジメントや川研修など、さまざまな研修を行ってきたけれど、私はその時「受講者」として受け身の姿勢でしかなかったのだと、実際に現場に出て、人の前に立つことで痛感しました。 キャンプの中では、裏で作業をするばかりではなく、道具の使い方の説明や、長老(現場責任者)がいないときなど、みんなの前で話をするチャンスもたくさんありました。しかし、いざ実際に前に立って話してみると、話が長くなってしまったり、淡々として面白さがなかったり、こどもたちを引き付けられず、なかなか思うようにいきませんでした。キャンプ前にリスクマネジメントや川研修など、さまざまな研修を行ってきたけれど、私はその時「受講者」として受け身の姿勢でしかなかったのだと、実際に現場に出て、人の前に立つことで痛感しました。今までの私は、学びたいという意欲はあっても、それを自分が得たときにどう自分のものにして次につなげていくのかという視点に欠けていたと思います。将来学校の先生になり、親になり、こどもたちに伝えていく場を多く持ちたいと思っているからこそ、何を伝えるか、どうやって伝えるか、本当に自分ひとりで伝えることができるのか、という意識を改めて強く持ち、残り7か月を過ごしていきたいと思います。 |
||
□ 研修担当おぐのふりかえり  7月から8月にかけて暮らしの学校だいだらぼっちは夏休みになり、山村留学のこども達はそれぞれの実家に帰ります。そして入れ替わりに、夏休み期間中開催される信州こども山賊キャンプの参加者が全国各地から集まってくるのです。まりおは実家に帰るだいだらぼっちのこども達を送り出した後、山賊キャンプを裏方で支えるスタッフの手伝いや、山賊キャンプの現場スタッフとしてこども達とキャンプを行いました。 7月から8月にかけて暮らしの学校だいだらぼっちは夏休みになり、山村留学のこども達はそれぞれの実家に帰ります。そして入れ替わりに、夏休み期間中開催される信州こども山賊キャンプの参加者が全国各地から集まってくるのです。まりおは実家に帰るだいだらぼっちのこども達を送り出した後、山賊キャンプを裏方で支えるスタッフの手伝いや、山賊キャンプの現場スタッフとしてこども達とキャンプを行いました。振り返りでは、この2か月の経験を題材に彼女の「原動力は何か」ということを言葉にする努力をしてもらいました。将来、教員になったとすれば様々な困難な状況も訪れることになるでしょう。そんな時に、自分が生き生きとこども達と過ごすことのできる原動力を思い返し「それでも、こどもと一緒に頑張れる」と思えるものを、持っていてほしいと思ったのです。 「みんなで支えあって、自分も誰かのためにって思えることが楽しい」「一緒に働く仲間がいるから頑張れる」「こどもと一緒に夢を実現して、その過程でこどもが何かできるようになることがすごくうれしい」まりおの言葉からは、彼女を動かす沢山の“人”の存在を感じました。人に支えてもらうこと、人を支えることの喜びを自分の中に見出していることは、彼女の素晴らしい力になっているでしょう。 1年間を通じて、こどもと共に歩むことの面白さや喜びを感じる経験がこれからもたくさんあるはずです。これからも、それを自分の原動力として積み重ね、教育を志す礎としてほしいと思います。 |
||
| 6月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
振り返ること、気に掛けることの大切さ  6月はこどもたち一人一人をもっとよく知ろうと毎日こどもたち18人との関わりの記録をつけることを始めました。一日の終わりに振り返りの機会を作ったことで、「今日はこの子とあまり関われなかったから、明日は隣に座ってごはんを食べようかな。」と考え、次の日にコミュニケーションをとるためのきっかけを作ることができました。こどもたちが学校から帰ってきてから寝るまでの短い間で18人全員と均等にコミュニケーションをとることは難しいことです。意識しないと1日ほとんど会話をすることなく過ぎていってしまう子もいます。何もしなければそのまま日々は過ぎていってしまうけれど、たとえ会話ができなかったとしても、1日1回でもその子のことを思い浮かべ、どんな様子なのかを考えるだけでも何かお互いに感じることは変わってくるのではないかと、1か月実践をしてみて感じました。目に見えるような効果はまだ分からないけれど、続けることで信頼関係づくりの幅が広がるのではないかということを信じて、残りの9か月間関わりの記録を続けたいと思います。 6月はこどもたち一人一人をもっとよく知ろうと毎日こどもたち18人との関わりの記録をつけることを始めました。一日の終わりに振り返りの機会を作ったことで、「今日はこの子とあまり関われなかったから、明日は隣に座ってごはんを食べようかな。」と考え、次の日にコミュニケーションをとるためのきっかけを作ることができました。こどもたちが学校から帰ってきてから寝るまでの短い間で18人全員と均等にコミュニケーションをとることは難しいことです。意識しないと1日ほとんど会話をすることなく過ぎていってしまう子もいます。何もしなければそのまま日々は過ぎていってしまうけれど、たとえ会話ができなかったとしても、1日1回でもその子のことを思い浮かべ、どんな様子なのかを考えるだけでも何かお互いに感じることは変わってくるのではないかと、1か月実践をしてみて感じました。目に見えるような効果はまだ分からないけれど、続けることで信頼関係づくりの幅が広がるのではないかということを信じて、残りの9か月間関わりの記録を続けたいと思います。素直に向き合うこと  6月に入り、こどもたちだけでなく私自身も徐々に気負いすぎることなく過ごせるようになってきました。4,5月は「こどもが主役の暮らし」ということを深く考えすぎて、大人としてどうこどもたちと関わらなければいけないかということに縛られすぎていたと感じています。大人だからちゃんとしないといけないという思いがずっと心のどこかにあり、話し合いなどでも大人として適切な意見を言わなければいけないと思って、自分自身を勝手に窮屈にしていたと感じています。でもこのままではここでの暮らしを心から楽しむことができないと感じ、失敗や恥を恐れず、もっと勇気を出そうと決めました。私は大人としてここに来ているけど、何が正しくて何が間違っているか分からないことはたくさんあるし、こどもたちと一緒になって考えればいい、私だってこどもたちと同じように目標を持ってチャレンジするためにここに来たのだから、このままではもったいないと思い、より素の状態でこどもたちと接してみることにしました。 6月に入り、こどもたちだけでなく私自身も徐々に気負いすぎることなく過ごせるようになってきました。4,5月は「こどもが主役の暮らし」ということを深く考えすぎて、大人としてどうこどもたちと関わらなければいけないかということに縛られすぎていたと感じています。大人だからちゃんとしないといけないという思いがずっと心のどこかにあり、話し合いなどでも大人として適切な意見を言わなければいけないと思って、自分自身を勝手に窮屈にしていたと感じています。でもこのままではここでの暮らしを心から楽しむことができないと感じ、失敗や恥を恐れず、もっと勇気を出そうと決めました。私は大人としてここに来ているけど、何が正しくて何が間違っているか分からないことはたくさんあるし、こどもたちと一緒になって考えればいい、私だってこどもたちと同じように目標を持ってチャレンジするためにここに来たのだから、このままではもったいないと思い、より素の状態でこどもたちと接してみることにしました。 食事をした後の机が汚かったり、宿題がなかなかできなかったりしてこどもたちに声をかけたりすることは4,5月もありました。でも今までは「大人だから言わないと」と思っていたのが「自分が気になるし、やった方がいいと思うから」と理由づけが変わっただけで自分の中の気持ちがとても楽になりました。こどもたちとイベントを計画する時にも、どんな内容にするか考えることを一緒に参加する仲間として心から楽しめるようになり、途中で投げ出し、自分勝手に行動しようとする子には心から「それはおかしいんじゃないの?」と疑問を投げかけられるようになりました。 食事をした後の机が汚かったり、宿題がなかなかできなかったりしてこどもたちに声をかけたりすることは4,5月もありました。でも今までは「大人だから言わないと」と思っていたのが「自分が気になるし、やった方がいいと思うから」と理由づけが変わっただけで自分の中の気持ちがとても楽になりました。こどもたちとイベントを計画する時にも、どんな内容にするか考えることを一緒に参加する仲間として心から楽しめるようになり、途中で投げ出し、自分勝手に行動しようとする子には心から「それはおかしいんじゃないの?」と疑問を投げかけられるようになりました。大人が何をどこまでやるかのバランスは難しく感じられるけれど、「大人だから」「こどもだから」とあまり難しく考えすぎず、大人であろうとこどもであろうと人対人であるということを忘れず、関わることができたらいいと思っています。その中でも、私が今まで積み重ねてきた経験や思いから、やらなければならないことはちゃんとやるし、辛い思いをしている子には声をかけ、こども同士で感情がぶつかりあって、どうしようもない時には、大人として相談に乗ったり、一緒に考えたりすることができたらいいのではないかと思います。 7、8月に向けて  6月は登山に行ったり、食材以外はすべて現地調達のサバイバルキャンプをしたり、大変で疲れることばかりだけど、でもなぜか楽しいことがたくさんありました。ものづくりの先生ぎっくの刃物ワークショップを受けて刃物の成り立ちや私達とのつながりを知り、おもしろい!と感じることもありました。でもこれらの出来事を振り返ったとき、何が楽しかったのか、何が面白かったのか、突き詰めて考えるとよく分からない自分に気付きました。ただ楽しい、面白いで終わらせてしまってはもったいないし、その理由が分からなければ誰かに伝えることもできないと思います。7、8月はだいだらぼっちのこどもたちとの暮らし、教員採用試験、そして山賊キャンプと予定が盛りだくさんです。いろいろな経験をするなかでそこでしか味わえない感情があると思います。こどもたちとの関わりの振り返りだけでなく、その日その時にあったことから何を学ぶことができるのかということを振り返ることを大切にしたいと思います。 6月は登山に行ったり、食材以外はすべて現地調達のサバイバルキャンプをしたり、大変で疲れることばかりだけど、でもなぜか楽しいことがたくさんありました。ものづくりの先生ぎっくの刃物ワークショップを受けて刃物の成り立ちや私達とのつながりを知り、おもしろい!と感じることもありました。でもこれらの出来事を振り返ったとき、何が楽しかったのか、何が面白かったのか、突き詰めて考えるとよく分からない自分に気付きました。ただ楽しい、面白いで終わらせてしまってはもったいないし、その理由が分からなければ誰かに伝えることもできないと思います。7、8月はだいだらぼっちのこどもたちとの暮らし、教員採用試験、そして山賊キャンプと予定が盛りだくさんです。いろいろな経験をするなかでそこでしか味わえない感情があると思います。こどもたちとの関わりの振り返りだけでなく、その日その時にあったことから何を学ぶことができるのかということを振り返ることを大切にしたいと思います。 |
||
□ 研修担当みけのふりかえり  毎日毎日18人のこどもたち全員のことを振り返るというのは、言うほど容易くありません。それでもまりおはこの1カ月の間、一言しか浮かんでこなくてもいいから毎日続け、それを続けていく先に何かがあると信じてこの先も続けていくことを決めました。また、形にとらわれた関わりではなく、「まりお」としてどう考え、どう動くのか、ということに意味があると考え、そのように動いてきました。こどもたちに見えないところでこどもたちに心を傾け、考え、動くまりお。まりおの決めたらやり抜く「信念の強さ」と、誰の話も素直に聞き、自分の思うところも素直に話すことのできる「素直さ」は、そのまままりおの「誠実さ」につながり、それは何物にも代えがたい宝物であり武器であると伝えました。この先「大人として」「先生として」動くことも当然あると思いますが、最後は「人として」どうあるか、が大切だと思います。まわりにも自分にも誠実である人には必ず返ってくるものがあるはず。今持っているその「誠実さ」を持ち続けて、まりおの信じる道を進んでいってほしいと思います。残り9カ月もガンバレまりお! 毎日毎日18人のこどもたち全員のことを振り返るというのは、言うほど容易くありません。それでもまりおはこの1カ月の間、一言しか浮かんでこなくてもいいから毎日続け、それを続けていく先に何かがあると信じてこの先も続けていくことを決めました。また、形にとらわれた関わりではなく、「まりお」としてどう考え、どう動くのか、ということに意味があると考え、そのように動いてきました。こどもたちに見えないところでこどもたちに心を傾け、考え、動くまりお。まりおの決めたらやり抜く「信念の強さ」と、誰の話も素直に聞き、自分の思うところも素直に話すことのできる「素直さ」は、そのまままりおの「誠実さ」につながり、それは何物にも代えがたい宝物であり武器であると伝えました。この先「大人として」「先生として」動くことも当然あると思いますが、最後は「人として」どうあるか、が大切だと思います。まわりにも自分にも誠実である人には必ず返ってくるものがあるはず。今持っているその「誠実さ」を持ち続けて、まりおの信じる道を進んでいってほしいと思います。残り9カ月もガンバレまりお! |
||
| 5月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
謙虚にこどもたちと向き合うこと  だいだらぼっちでの生活がはじまり、2か月が経ちました。4月は暮らすというよりも非日常のキャンプに来ているような感覚でしたが、やっとだいだらぼっちが私たちの家であり、日常なのだという感覚が身についてきました。こどもたちもきっと同じような感覚で、5月に入り緊張が解け、今までは遠慮していたことなどもそうではなくなり、部屋中に洗濯物が散らばるようになり、ごはんづくりを途中で放ったらかして遊びに行ってしまったり、どっちがコップを片付けるかでケンカをしたりと、こどもたちの素が表れてくるようになりました。そんなこどもたちの様子に、「自分たちで決めた事なのになんでできないの?」と思ってしまうことがよくありました。そんな話をしていたときに、「こどもたちがいろんなことにチャレンジしたいと思えること自体すごいことなんだよ。それを謙虚に応援してあげることができるといいね。」という言葉をある相談員からかけてもらいました。 だいだらぼっちでの生活がはじまり、2か月が経ちました。4月は暮らすというよりも非日常のキャンプに来ているような感覚でしたが、やっとだいだらぼっちが私たちの家であり、日常なのだという感覚が身についてきました。こどもたちもきっと同じような感覚で、5月に入り緊張が解け、今までは遠慮していたことなどもそうではなくなり、部屋中に洗濯物が散らばるようになり、ごはんづくりを途中で放ったらかして遊びに行ってしまったり、どっちがコップを片付けるかでケンカをしたりと、こどもたちの素が表れてくるようになりました。そんなこどもたちの様子に、「自分たちで決めた事なのになんでできないの?」と思ってしまうことがよくありました。そんな話をしていたときに、「こどもたちがいろんなことにチャレンジしたいと思えること自体すごいことなんだよ。それを謙虚に応援してあげることができるといいね。」という言葉をある相談員からかけてもらいました。気持ちと言葉と行動がアンバランスで不完全なこどもたちのバランスを整えることも大切だけど、全員がすべてを完璧にこなすことは難しいと思います。だからこそ、アンバランスさを補い支えてあげることが今の私にできることなのかもしれないということを感じました。学校の宿題と向き合えない子がいたら、一緒に計画を立てて少しでも取り組めるように応援したり、木工をやりたいけど時間がないことを理由に取り組めない子がいたら、どうやったら時間を生み出せるか一緒に考えたりするなど、小さなことを積み重ね、こどもたちを応援したいと思っています。そのためにも、思いを伝えあい、どの部分を支えてあげるべきなのかに気付くことができるようになりたいと思います。 作ることは暮らしを豊かにする  私は毎日出される市販のおやつを見て、手づくりのおやつをみんなに出してあげられたら素敵だと感じ、週に1度のおやつづくりを始めました。こどもたちが「アイスが食べたいな〜」とつぶやいているのを聞いて、作ってあげたときには、「おいしい!明日も作って!」といって本当に喜んでくれました。その姿を見たとき、私は自然と笑みがこぼれ、温かな気持ちになりました。休日はこどもたちと一緒にお菓子を作り、「次はトルコアイスに挑戦したいね!」と、どんどん夢も膨らみました。 私は毎日出される市販のおやつを見て、手づくりのおやつをみんなに出してあげられたら素敵だと感じ、週に1度のおやつづくりを始めました。こどもたちが「アイスが食べたいな〜」とつぶやいているのを聞いて、作ってあげたときには、「おいしい!明日も作って!」といって本当に喜んでくれました。その姿を見たとき、私は自然と笑みがこぼれ、温かな気持ちになりました。休日はこどもたちと一緒にお菓子を作り、「次はトルコアイスに挑戦したいね!」と、どんどん夢も膨らみました。おやつづくりだけでなく、食器づくりや染物などのものづくりは、イベントとして行うことは楽しいけれど、それが日常になった途端に時間はかかるし面倒くさいと感じることがあります。私もここに来る前は、時間の効率化や便利さを優先し、作ることを遠ざけていました。しかし、当たり前のように手作りで日常を豊かにしているだいだらぼっちの人々と暮らし、私も暮らしをよくするためにものづくりをしたいと思うようになり、おやつを手作りにしてみよう、布を草木染めしてカーテンを作ってみよう、箸を自分で作ってみよう、など日常の中でのものづくりに挑戦しました。初めてのことも多く、作ったものは不格好なものばかりだけれど、いろんな人から教えてもらい、誰かのためを思って作ったり、夜遅くまで筋肉痛になるまで頑張ったりするなど、そこにはたくさんの思いが込められていて、どんなに高級な製品よりも貴重なものだと感じました。「箸が完成したから次はスプーンが欲しいなぁ。」などと次々ものづくりのアイデアが生まれ、楽しくて仕方がありません。この感覚は実際に自分で作ることでしか味わえないものであり、暮らしや人を豊かにするものなのだということを実感しました。 6月に向けて  5月は「こどもたちと謙虚に向き合う大切さ」、「作ることの豊かさ」を改めて実感することのできた1か月でした。6月はこの2つの実感したことを具体的に自分の行動に反映させることができるといいと思っています。 5月は「こどもたちと謙虚に向き合う大切さ」、「作ることの豊かさ」を改めて実感することのできた1か月でした。6月はこの2つの実感したことを具体的に自分の行動に反映させることができるといいと思っています。まず、こどもたちと謙虚に向き合うために、もっと「こどもたちを知る」ということができたらいいと思っています。こどもたちの中には、毎日自然と寄ってきてよく話す子もいれば、意識しないと1日一言もしゃべらず終わってしまう子もいます。なにかの縁でこの年に一緒に暮らすことになった仲間だからこそ、私は18人のこどもたち全員と向き合い、信頼関係を築きたいと思っています。そのために、6月は毎日こどもたち一人一人との関わりを簡単に記録し、一日の終わりに今日どんな関わりをしたか振り返ることで、全員とどんな風に向き合うべきか考える機会を増やしたいと思っています。 ものづくりもどんどん進めていきたいです。まずは木のスプーンを完成させること、週1おやつづくりを継続させることを来月の目標にして取り組んでいこうと思います。 |
||
□ 研修担当もーりぃのふりかえり  5月を終え、だいだらぼっちでの暮らしが、非日常から、日常になってきたと振り返るマリオ。何もかもが初めてだった4月にくらべ、暮らしにも慣れ、5月のマリオは、その旺盛なチャレンジ精神で、空いた時間を上手に使い、おやつ作りに、ものづくり、こどもたちと遊びの計画を立てるなど、暮らしを豊かにすることに挑戦していました。振替りでは、時間をかけて自分が感じたことに向き合ってもらいました。なかなか言葉にできない感情と向き合い、チャレンジしたことを整理して、言葉にしたり、納得したりすることが確かな学びにつながるのです。マリオがとても苦労して絞り出したのが、「謙虚に向き合う」「作ることの豊かさ」マリオ自身が体験し、自分と向き合い実感した学びです。たくさん考え抜いたマリオの言葉には、とても力強さがありました。 5月を終え、だいだらぼっちでの暮らしが、非日常から、日常になってきたと振り返るマリオ。何もかもが初めてだった4月にくらべ、暮らしにも慣れ、5月のマリオは、その旺盛なチャレンジ精神で、空いた時間を上手に使い、おやつ作りに、ものづくり、こどもたちと遊びの計画を立てるなど、暮らしを豊かにすることに挑戦していました。振替りでは、時間をかけて自分が感じたことに向き合ってもらいました。なかなか言葉にできない感情と向き合い、チャレンジしたことを整理して、言葉にしたり、納得したりすることが確かな学びにつながるのです。マリオがとても苦労して絞り出したのが、「謙虚に向き合う」「作ることの豊かさ」マリオ自身が体験し、自分と向き合い実感した学びです。たくさん考え抜いたマリオの言葉には、とても力強さがありました。自分と向き合うことで、6月に向け明確な課題も見えてきたようです。もう一方では、やりたいことがどんどんと出てきているのだそうです。「こどもたちがいて、ものづくりを身近に感じられる今の暮らしがとても楽しい!」とやる気に満ちていました。たくさんの体験をしっかりと学びに変え頑張っていってほしいと思います。 |
||
| 4月育成プロジェクトまりお研修報告 | ||
 はじめに はじめに私は3月に大学を卒業し、だいだらぼっちに来ました。大学時代には山賊キャンプのボランティアに参加し、そこでの経験もきっかけとなり、大学卒業後は教師になりたいと思うようになりました。卒業後すぐに教師になるという選択肢もあったのですが、だいだらぼっちの人々やその暮らしに惹かれ、ここで学びたいと感じ、育成プロジェクトに参加しました。私は、ここで学ぶにあたり、こどもたちと「どう信頼関係を築いていくか」を学ぶというテーマを考えました。私自身、学生時代にお世話になり、心から信頼している先生や大人に教えてもらったことやかけられた言葉はよく覚えていて、私が物事を考えるときのヒントや力になっています。そんな信頼関係を私もこどもたちとの関わりの中で結び、将来こどもたちの力になりたいと感じています。しかし、そのためにどうすればいいのかはよく分からず、1年間実体験を通して学んでいこうと考えました。 4月振り返り  はじめは緊張と不安でどうしていいのか分からず、先輩相談員や継続のこどもたちに何をすればいいかを聞き、覚えることに必死な毎日でした。学校からこどもたちが帰ってくると毎日のように話し合いをして、暮らしについて知っていきました。早速田んぼ作業や薪作業、毎日のごはん作りや風呂焚きなども始まりました。村役場や近所の村の人のお家にあいさつに行ったり、村の道路掃除に参加したりもしました。初めてのことばかりの中で、薪作業の計画の話し合いの中身がよくイメージできなかったり、知らない用語がたくさんでできたりして、戸惑うこともありました。こどもたちとの関わりについても、他の相談員たちは私の気付かないこどもたちの悩みや変化に気付いていたり、話し合いなど大事な時に大事なことを伝えるということをしていたりして、自分にはそんな余裕がなく、気づくことが少なかったと感じています。とにかく盛りだくさんの毎日で、その暮らしについていくこと、自分の中で暮らしのリズムを作っていくことで精いっぱいだったような気がします。 はじめは緊張と不安でどうしていいのか分からず、先輩相談員や継続のこどもたちに何をすればいいかを聞き、覚えることに必死な毎日でした。学校からこどもたちが帰ってくると毎日のように話し合いをして、暮らしについて知っていきました。早速田んぼ作業や薪作業、毎日のごはん作りや風呂焚きなども始まりました。村役場や近所の村の人のお家にあいさつに行ったり、村の道路掃除に参加したりもしました。初めてのことばかりの中で、薪作業の計画の話し合いの中身がよくイメージできなかったり、知らない用語がたくさんでできたりして、戸惑うこともありました。こどもたちとの関わりについても、他の相談員たちは私の気付かないこどもたちの悩みや変化に気付いていたり、話し合いなど大事な時に大事なことを伝えるということをしていたりして、自分にはそんな余裕がなく、気づくことが少なかったと感じています。とにかく盛りだくさんの毎日で、その暮らしについていくこと、自分の中で暮らしのリズムを作っていくことで精いっぱいだったような気がします。 しかし、新鮮な暮らしの中で楽しさや新たな発見をすることもありました。村のおばあちゃんのお家に行って村の歴史や日々の暮らしについて話を聞いたり、ものづくりはただ作るのではなく、暮らしの中の必然から生まれるということを相談員から教えてもらったりして、新しいものの見方も生まれました。そして、四季の変化を気にするようになり、暮らしとは何か、習慣や伝統が受け継がれてきた意味をもっと知りたいと思うようになりました。だいだらぼっちでは、こどもたちとの関わりだけでなく、様々な角度から様々なことが学べるのだということに気が付きました。 しかし、新鮮な暮らしの中で楽しさや新たな発見をすることもありました。村のおばあちゃんのお家に行って村の歴史や日々の暮らしについて話を聞いたり、ものづくりはただ作るのではなく、暮らしの中の必然から生まれるということを相談員から教えてもらったりして、新しいものの見方も生まれました。そして、四季の変化を気にするようになり、暮らしとは何か、習慣や伝統が受け継がれてきた意味をもっと知りたいと思うようになりました。だいだらぼっちでは、こどもたちとの関わりだけでなく、様々な角度から様々なことが学べるのだということに気が付きました。まとめと課題 4月は自分から新しいことに挑戦するというよりは、新しく与えられた環境の中でどう過ごすかを考えることが多かったと感じています。自分に余裕がなくあっという間に1か月が過ぎてしましました。来月はもっと時間を上手く使って、ものづくりや村歩きなどにどんどん挑戦したいと思っています。その中で、こどもたちとの時間を第一に、一緒に料理、風呂焚き、イベントなどに取り組むだけでなく、食事中のさりげない会話なども大切にしていきたいです。そして、こどもたちのことをもっと知ることで信頼関係を結ぶことにもつなげていくことができたらいいと考えています。 |
||
□ 研修担当つぅのふりかえり  いろいろ悩み育成プロジェクトの参加を決意し、不安だらけの4月がスタートしたと思います。しかし、だいだらぼっちの生活がスタートしたらその不安も少しずつ解消され、いろいろな発見と学びがあったと思います。 いろいろ悩み育成プロジェクトの参加を決意し、不安だらけの4月がスタートしたと思います。しかし、だいだらぼっちの生活がスタートしたらその不安も少しずつ解消され、いろいろな発見と学びがあったと思います。あまり深く考えても、行動しなければ結果は出ません。だいだらぼっちの生活が始まれば不安に抱く時間もあまりありません。ナイトハイクや薪作業などイベントも盛りだくさんで考えることよりも感じることの方が多かったようです。 こどもたちとの生活では毎日が試されることがあり、また思うように運ばないことも多々あります。最初は戸惑うことや悩むこともあるかと思いますが、そのなかでこどもたちとコミニュケーションをとり関係性を築いてほしいです。また、こどもたちの安心できる居場所として今後どんなことに気を付け、どんなことをするか今後の課題でもあると思います。自分だけの価値観だけではなく、たくさんのこどもたちの触れ合うことでいろいろな考え方や価値観を磨いていってほしいです。 |
||
| 育成プロジェクト TOP | ||
* 問い合わせ・連絡先 * 〒399−1801 長野県下伊那郡泰阜村6342-2 TEL:0260-25-2172 FAX:0260-25-2850 e-mail camp@greenwood.or.jp |
