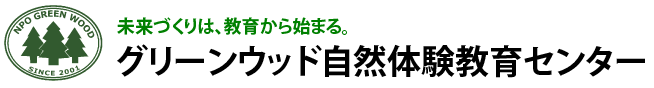今年度もあと2カ月を切った。すでにご存じの通り、私は4月から、大学教員にチャレンジしている。泰阜村の政策アドバイザーでもあるから、何足もわらじを履いている。
大学とは、青森大学。国立大学ではない。青森の国立大学は弘前大学。サッカーの強い青森山田学園の大学といえばわかりが良いだろう。そしてほぼ100%の人が「またずいぶんと遠いところの…」と感想を持つ。実は青森大学は、東京の江戸川区に東京キャンパスを持っている。その東京キャンパスの専任教員(社会学部)だ。私は修士も博士も持っていないため、研究者学歴としてはゼロに等しい。しかし、30年の実践や、著書を含めた数々のアウトプットが、それらと同等の価値を持つと認められた。率直に、認めていただき嬉しく想う。
さて、東京キャンパス自体はまだ4年目。しかも、様々な事情があって9割以上が留学生。すべての仕事が困難を極めていることは想像に難くないだろう。留学生も、教職員も初めてのことばかりなのだ。そして、異なる文化を持つ留学生同志が学問を究めることも、コロナ禍で学びを紡いでいくことも、本当に難しいことばかりだ。正直なところ、立ち止まってしまう場面も多い。
しかし、だ。この混沌さを「非生産的だと想う」か、「豊かなことだと想う」かは、決定的に違ってくる。私は、後者の想いに立つことが、多様性を認め合い、未来を生きるチカラを生みだすということを、私は30年のNPO実践から経験的に学んでいる。
この大学は、少人数学生を受け持つ担任制をとっている。私も、なんと1年生5人、2年生11人、3年生5人、すべての学年(社会学部はまだ始まって3年目)の担任だ。履修科目の指導に始まり、アルバイトや生活の相談、ビザ更新や帰国について、そして就活についても面倒をみる。大学生にもなって担任か、と想うだろうが、相手は日本語もままならない留学生だ。しかもこのコロナ禍のなか、帰国もできずにいた2年間は、ともすれば学びをたやすく諦めてしまうような状況にもあった。それを全力でサポートすること、つまりは安心できる環境を創ることこそ、学びの第一歩だと考えているからこその担任制だ。
親元を離れて異文化の地に身を置き、さらに多様な文化を持つ学生と切磋琢磨する。その学生生活から生まれるかすかな学びを、丁寧に拾い上げて支えていく。これを繰り返す地道な10カ月だった。我ながら、よくやっていると想う。
あれ? でも待てよ。この感覚、どこかで感じたぞ。デジャブのようだ。
そう、長野県泰阜村で30年間、持ち続けてきた感覚なのだ。私は確かに、「留学生」と30年間向き合ってきた。それは留学生といっても、小中学生と、少々幼い。しかし、暮らしの学校に参加する幼い留学生も、青大東京キャンパスに通う大学生の留学生も、自分の意志でその学びの場に立ち、学びの場を紡ぐ主人公であることに、間違いない。泰阜村でも、今東京でも、想い通りにならないことばかりだが、そこをいかに楽しめるか。30年間で鍛えられた逆境を楽しむセンスを、今、東京の留学生たちと共有している。
結局「留学生」と向き合う30年だった。いや、これからも続く。つくづく他の地域で学ぶ可能性を探って来たな、と想う。つくづく多様な価値観に身を置くことで学ぶ可能性を追い求めているな、と想う。
留学。留まって学ぶその意義は? 可能性は? いったい何だろう。NPOグリーンウッドは、2001年にNPO法人化する前、「グリーンウッド遊学センター」という任意団体だった。遊学とは、遊んで学ぶ、というそのものの意味だけではない。遊説という言葉があるように、遊学とは本拠地を離れていろいろな土地で学ぶこと、を意味する。
想えば私も、故郷福井から大学4年間、札幌に留学したのだ。その後30年間は泰阜村に留学、今東京にも留学していることになる。遊びを仕事にしたなあ笑 そして学びを仕事にもした。今52歳。遊んで学んで、そして「遊学」の途中だ。留学と遊学という言葉に、今はそこまでこだわる必要はない。が、私は次の10年は、留学・遊学の意義と可能性を、もっとダイナミックにとらえた活動を展開する中で、そこはこだわって深めていきたいと想う。
「奇跡のむらの物語~1000人の子どもが限界集落を救う!~」
私が11年前に出版した本である。
先日、出版社から連絡があった。重版ということらしい。そもそもそんなに普及されるとは思っていなかった。何十万部と売れているわけではないから、重版といってもおそらくロットは少ない。それでも、重版と聞くと、書いた張本人としてはうれしいものだ。
東日本大震災の2011年に出版。その後、何度か増刷があり、現在7刷。ハングルに翻訳されて、韓国でも出版されてはいる。決してベストセラーではない。そんなわけがあるはずがない。でもね、みなさん。
おおがかりな宣伝や広告をすることなく、静かにじわじわと読者が広がっていく様。それはなんだか、私たち泰阜村の生き様らしいではないか。読んだ人からの読みうつし、口うつし、手うつしで、この本が広がっているといいな。そしてこの本に記された内容や想いも広がっていくといいな。ベストセラーよりロングセラー。そんな本であってほしい。
東日本大震災の大混乱の最中に世に出された。そして今、コロナウィルス、ウクライナ戦争、未曽有の円安など、大混乱の中で、再び世に出されていく。宣伝するつもりはまるでないが、もしお時間があるようならぜひお読みいただきたい。
今一度、11年前に書評などで紹介された記事を2つほど紹介する。
●日本教育新聞の書評記事●
「協働が生む村に回帰の教育」
過疎の村に子どもたちの声が響く、それだけで村が元気になる。かつて短期山村留学を仕掛けた地元の人たちからこんな思いを聞いた。だが熱い思いがあったとしても継続させていくことは難しいという現実が一方にはある。
本書が紹介する山村留学はとてもパワフルだ。舞台は長野県下伊那郡泰阜村。25年前に仕掛けたのは、地元の人たちではなく、「ヨソモノ」のNPO法人グリーンウッド自然体験教育センターの若者たち。「山村」「教育」「NPO」の「金にならない3点セット」が常識を覆す。村人を巻き込み、全国の若者を巻き込み、活動自体が活性化し、発展していく。
村の暮らしの学校「だいだらぼっち」から、文科省・農水省連携事業の「子ども長期自然体験村」事業を契機に、村人との協働がスタート。村の住人を山賊に見立てる「信州子ども山賊キャンプ」には、夏と冬の長期休暇中、人口1900人の村が、千人を超える子どもと300人を超える青年ボランティアリーダーでにぎわう。村人自身も加わって、「案じることはない」という意を持つ、「あんじゃね自然学校」が生まれ、運営のかじ取りを話し合う会議「あんじゃね支援学校」で大人たちが学び合う。
「村を捨てる教育」から、村に回帰する教育へと大きく変貌する様子がわかる。今、教育に何が足りないか、痛感させられる快著
●日本農業新聞の書評●
「山村留学で価値見直す」
東京から高速道路を使って5時間以上もかかる長野県泰阜村で、1986年からある特定非営利活動法人(NPO法人)が山村留学を始めた。エコロジーとう言葉もなかった時代、この村の環境こそが子どもたちを健やかに育むと信じて活動をスタートさせた。本書は、NPOメンバーの25年間にわたる活動を振り返ったノンフィクションだ。
全国から村に集まった子どもたちは、共同生活を送りながら、自分たちで田畑を耕し、食事を作り、薪で五右衛門風呂を沸かす。山や川で遊び、時には村の猟師が罠で捕まえたイノシシの解体に立ち会う。なんとも不便で、そしてこれ以上にないほどに贅沢だ。読むほどに、ここで暮らし、学ぶ子どもたちがうらやましく思われてくる。
「わしゃ、そこにある山をどかしてほしいと、いつも思っていた。不便だし・・・中略・・・でもな、都市の子どもと触れ合うことで山の持つ価値がわかった」
当初、活動に懐疑的で非協力的だった住民も、徐々に自分たちの持つ財産に気づき始めた。子どもたちが目を輝かせて戯れる川、空、星、田んぼ、そして村人の知恵。子どもたちと触れ合う村の老人たちは「限界集落ではなく“現役集落”」と胸を張る。
今では、村とNPOが一体化、さまざまなプロジェクトを立ち上げるが、その信頼関係は一朝一夕に築かれたものではない。
不便で、何をやるにも時間がたっぷりかかる。それでも、こんな素敵な村をつくれるなら悪くない。日本全体が立ち止まり、自分たちが進む道を考えるべき今、この本から学ぶことは多い。